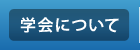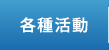学会について
会長挨拶
2025年 年頭所感
|
2025年が、世界の子どもたちとそのご家族、そして日本小児科学会の会員の皆さまにとって、希望に満ちた素晴らしい年となりますよう、心より祈念申し上げます。
2024年は、社会がCOVID-19感染拡大によるパンデミック後の新たな日常を築きつつ、少子化の進行、医師の働き方改革など多様な課題に直面した一年でした。このような状況の中で、会員の皆さま方におかれましては、診療や教育、研究を通じて、子どもたちの健康と福祉を守るために奮闘を続けてこられたものと、敬意の念を表します。 さて、2024年の出生数の公式統計はまだ発表されておりませんが、上半期の出生数は32万9、998人と報告されており、最終的には2023年の年間出生数75万人を大きく下回ることが予測されています。少子化が一層進行する中、昨年から1か月児および5歳児健康診査支援事業が導入され、新生児拡大マススクリーニングの実証事業も開始されました。これらの施策は、少子化問題に対応するための重要な取り組みであり、子育てを支援する医療保健活動の重要性はますます高まっていると考えられます。本学会としても、1か月・5歳児健診推進アドホック委員会を設置し、国による支援事業の適切な運用と健診の円滑な実施体制構築の支援を進めております。
|
公益社団法人日本小児科学会 会長 滝 田 順 子 |
日本小児科学会会長就任のご挨拶
令和 6 年 4 月20日に日本小児科学会会長を拝命いたしました京都大学大学院医学研究科発達小児科学の滝田順子でございます。
本学会は明治29年(1896年)に小児科研究会として発足しました。その後、明治35年(1902年)には会則が改変され、日本小児科学会に改められました。小児科研究会の発足から数えますと、およそ130年の歴史をもつ伝統ある本学会において、女性の会長は初めてでありますので、大変身に余る光栄であり、かつその重責に身が引き締まる思いです。伝統の中にもリベラルが共存する大変素晴らしい環境を築き上げてくださいました偉大な先輩方、会員の皆様方に心より感謝申し上げます。
日本小児科学会の目指すものは、定款を紐解きますと、小児科学に関する研究と小児医療との進歩、発展をはかるとともに会員相互の交流を促進し、小児医療の充実、子どもの健康、人権および福祉の向上、さらにこれらを社会へ普及啓発すること、と記載されております。このミッションを果たすためには、こどもたち、日本小児科学会、小児医療を取り巻く社会環境の課題を解決することが急務と考えます。
まずこどもたちを取り巻く環境の課題として第一にあげられるのは、少子化の進行です。2023年には出生数75万人台と過去最低の数字が示されました。その一方で、生命を脅かすような重大ないじめや児童虐待件数は増加傾向にあり、それに呼応するように小・中・高生の自殺者も年々増加傾向にあります。つまり生まれるこどもは少なくなる一方で、こどもの生命の危険は高まっている状況となっています。そんな中、2018年には成育基本法が成立し、また2023年には、こどもが真ん中の社会を実現するためにこども家庭庁が発足しました。この環境の変化を受けて、私ども小児科医は、行政とも連携し、生まれたこどもを失わない、心身ともに健やかな成長を支援する必要があります。1か月児と5歳児の健康診査支援事業の推進は、こどもの健康を守るためには大きな加点になるものと期待されますが、思春期以降の青少年に対する健康管理も重要な課題と考えます。
次に小児医療を取り巻く環境の特徴として、疾患構造の変化が挙げられます。Common Diseaseが減少する中で難病のキャリアや超低出生体重児が増加し、複雑かつ濃厚なケアが必要な医療的ケア児が増加しております。さらに最近、医薬品の供給不安、診療報酬改定、ドラッグラグの問題といった新たな課題も浮かび上がっています。これらの課題解決に向けて、地域の小児医療提供体制の維持と均てん化、またアクセス性の向上や療育環境の更なる整備が求められると思います。一方、小児科医を取り巻く社会環境における最近の大きな変化としては、2018年から開始された新専門医制度、それから今年の4月にいよいよ開始された医師の働き方改革が挙げられます。さらにNature誌でも取り上げられましたが、現在、日本の研究力の低下が深刻な問題となっております。また他方、小児科専攻医のうち女性の割合は概ね40 %程度が継続しておりますが、国試合格者の中で女性は30 %程度なので、小児科は女性医師の割合が多い診療科といえます。そこで、次世代を担う若手小児科医の確保・育成、ダイバシティ―の推進、研究力の促進が今後の重要な課題と考えられます。
私は、本学会会長として、これらの課題解決のために、次の5つの挑戦に取り組みたいと考えております。まず、第一の挑戦として小児医療提供体制の更なる充足と質の均てん化(オンライン診療やこども・青年のメンタルヘルスケアの推進)を進めます。第二の挑戦として、次世代を担う若手医師の育成(サブスペシャルティ専門医制度の整備構築、適切なキャリア支援)、第三の挑戦として、ダイバシティーの推進(女性・若手医師の業務環境の整備、働き方改革の適切な対応)に取り組みます。第四の挑戦として、小児医療の研究とイノベーションの推進(リサーチマインド、国際化の推進)、また第五の挑戦として機動力と発信力のある学会・理事会運営(委員会活動の活性化、理事会の効率化、行政との連携)に臨みます。
そして、これらの挑戦を成し遂げた先に全てのこどもたちと次世代の小児科医に輝かしい未来と夢を届けるフロントランナーとして、お役に立ち続けたいと願っております。
今後ともどうかよろしくご支援、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。