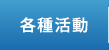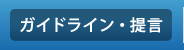ガイドライン・提言
乳児の安全な睡眠環境の確保について
2024年改訂「寝ている赤ちゃんのいのちを守るために」(こども家庭庁)に関する見解
(日本小児科学会理事会承認日 令和7年1月28日)
公益社団法人日本小児科学会
要旨
乳児の安全な睡眠環境の整備の推進は、窒息事故および乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防に寄与する。この啓発のためのリーフレットにおける寝具に関する推奨改訂に関して、以下の見解を表明する。
1. わが国でも寝具の関与が疑われる乳児死亡は相応に発生しており、啓発の意図は適当といえる。
2. 一方で、過度に具体的で一律的な規制表現は、保護者や保育関係者等に混乱を招く可能性がある。特に、「上にかけるふとんは使わない」といった表現は現実的でないと受け取られる場合があり、このような一部の表現が受容されにくいことで、リーフレット全体のメッセージへの信頼や受容度が低下する懸念がある。この点を踏まえ、以下の追記修正等を要望する。
| a. | 掛けぶとんの「使用禁止」は、他省庁等による推奨ほか現状との乖離が大きく、また禁止とした場合の代替策やその安全性についても現時点ではエビデンスが十分とは言えない。当該表現を「使用禁止」と受け取られないようにするとともに、推奨の実現性、有効性、妥当性を確認し、必要に応じて、推奨理由の丁寧な解説・補足をすることが望まれる。 |
| b. | 掛けぶとんを使用しないことを推奨する対象を、月齢2(〜3)から月齢12(〜13)までに限定することが望まれる。ただし実施困難な場合に限っては、生後から1歳になるまで使わないとする推奨も否定はされない。 |
| c. | 掛けぶとんを使用しないことを推奨する対象から、適切な監視(心拍呼吸の医療的な機械監視を含む)が行われ必要時に直ちに介入できる医療機関、保育施設や産後ケア施設等の環境を除外する運用を考慮されたい。ただし家庭用モニターは代替として適切とはいえない。 |
| d. | 掛けぶとん以外の寝具やその他の睡眠環境、例えば「添い寝」に関しての検討も、今後行われるべき課題である。 |
| e. |
乳児用スリーパー、ベッド・イン・ベッド等の保温のための代替案について、適切な使用法とともに具体的に分かりやすく提案されるべきである。ただし、乳児の寝具につきわが国での安全基準の確立が急務である。
|
3. 本邦の実態に基づいた疫学的な解析と実効性のある提言を可能にするためには、国内におけるチャイルド・デス・レビュー制度の確立が強く望まれる。
はじめに
公益社団法人日本小児科学会は、予防のための子どもの死亡検証委員会、こどもの生活環境改善委員会、小児救急・集中治療委員会の関連3専門委員会の合議および理事会による審議により、こども家庭庁によるSIDSの啓発用リーフレット「寝ている赤ちゃんの命を守るために」1)(以下、リーフレットと略)の内容等について以下の見解を発表する。
背景
わが国で0歳児の死亡は年間1,500ないし2,000件発生し、その原因として先天奇形等、呼吸障害等、不慮の事故、乳幼児突然死症候群(SIDS)等が上位に挙げられる2)。これら「不慮の事故」の大半は、睡眠中に発生する窒息事故である。米国のレジストリ研究では、乳児突然死の72%は「安全でない睡眠環境」で発生しており、窒息(確定および疑い)例の74%は柔らかな寝具(soft-bedding)が関与すると報告された3)。またSIDSは「それまでの健康状態および既往歴からその死亡が予測できず、しかも死亡状況調査および解剖検査によってもその原因が同定されない、原則として1歳未満の児に突然の死をもたらした症候群」と定義され、主として睡眠中に発症する4)。SIDSの発生には様々な誘因が関与するとされ、うつ伏せ寝をはじめとする「安全でない睡眠環境」も外部要因のひとつとされる5)。安全な睡眠環境の整備の推進は、窒息予防にもSIDS予防にも寄与することが、強く期待される。
このたびこども家庭庁より発出のリーフレット1)は、その記載内容を見るかぎり、乳児にとって安全な睡眠環境について啓発する目的によるものと理解できる。従って、このような文書等を策定することに関しては、本学会としても支持するものである。2023年度まで当該文書は広く国民及び関連団体等に周知され、大きな混乱をきたすことなく啓発のため用いられてきた背景を鑑みると、これについて改めて本学会から見解等を発出する必要はないものと認める。
一方で、2024年度版より同リーフレットに新たに追記訂正された内容については、その妥当性や有効性等について未検証であり、その解釈等をめぐって混乱を生じうる懸念もありうる。従って、本学会として、上述の3専門委員会の合議をもとに、この部分についての見解を表明するものである。
なお、こども家庭庁より本学会に諮問依頼のあった当該リーフレットへの追記(案)「SIDS の普及啓発用リーフレット等の補足説明について / ※米国小児科学会による睡眠環境下の死亡を減らすための推奨事項(2022 年版:以下抜粋(仮訳))を参考にしております。/ 『SIDSや窒息、ベッドの隙間等に挟まることによる機械的窒息、首の絞扼のリスクを減らすために、枕や枕のようなおもちゃ、キルト、掛け布団、ベッドパッド、毛皮のような素材、ベッドに固定されていない寝具(例えば、ブランケットやゴムのついていないシーツ)などの柔らかい物は、(生後 1 歳までの)乳児の寝床から遠ざけてください。』」については、引用された文献6の妥当性について、本学会にて別途審議を行った。実績のある学術団体によって十分な調査とエビデンスに基づいて発出された報告であり、当該文書への引用方法も、適切と認められる。さらに、その日本語訳として「(生後1歳までの)」と原文にはない追記がなされた背景として、引用元文献は乳児に限定した推奨を報告するものであるところ、リーフレット原文では年齢を問わない推奨であるかのような誤解を生じかねない表現であったことから、引用・転載の方法についても適切であると考えられた。(注記:本見解の発出準備中の2024年12月25日に、この追記についてはこども家庭庁のwebページに掲載され一般公開された 18)。)
見解
リーフレットにおいて、2024年版における変更点は、乳児用の(軽い)掛けぶとんを使うとする従来の記載を「上にかける布団は使わない」「掛けぶとんは使用せず、服装で温度調整しましょう」1)と、寝具に関する推奨を改めた点である。そこで本見解では当該部分を検討の対象とする。追記文(案)を勘案すると、当該改訂は米国における推奨6)を日本国内に展開することを意図した記載と解される。
米国の一般国民を対象とした調査7)では、「(調査に回答した母親のうち)3人に1人以上が乳児の睡眠環境で柔らかい寝具を使用していると回答した」と報告され、その柔らかい寝具として「最も多く報告された柔らかい寝具の種類は、バンパーパッド(19.1%)、ふわふわまたは厚手の毛布(17.5%)、次いで枕(7.1%)、乳児用ポジショナー(6.2%)、ぬいぐるみ(3.1%)が続く」と列挙された。また米国の死亡登録では乳児突然死の14%が窒息であり、これら窒息事例の69%に柔らかい寝具が関連し、そのうち34%は毛布(類)による気道閉塞であった8)。米国消費者製品安全委員会の登録情報では、乳児窒息死に寄与した寝具類は、枕(24.5%)、毛布(13.1%)、掛けぶとん(1.4%)等であり、特に毛布と枕について「乳児の睡眠環境にこれらが存在することは懸念されるべきであり、予防の努力を続ける重要性が強調される」と報告された9)。このように柔らかい寝具環境で乳児を寝かせることが一定の頻度で観測される米国において乳児の睡眠環境の改善を目的として、文献6はダイジェストにおいて「...掛けぶとん...等の柔らかい物体、毛布...等のゆるい寝具を、乳児の睡眠エリアから遠ざけるように」とし、詳細表記において「柔らかい(soft)物体やふにゃふにゃ(loose)な寝具は、乳児の口鼻を閉塞しうる。これらは乳児の窒息事故の最多の原因である」、さらに「重い毛布、重いスリーパー、重いおくるみ、またはその他の重い物体を、眠っている乳児の上や近くに置かないことを推奨する」と追記された。
一方、わが国の乳児の窒息死に関する報告は限定的である。複数施設の乳幼児突然死の法医解剖例をまとめた報告10)では、乳児窒息死230例の睡眠環境について「添い寝の有無」「発見時の体位」が検討されたが、寝具の解析はなされなかった。別の報告11)では、乳幼児突然死の法医解剖例の寝具について、26%が大人用ベッド、39%が大人用ふとん、10%が乳児用ベッド、14%が乳児用ふとんで寝かされていたことが示されたが、死亡原因には言及されなかった。単施設の剖検例をまとめた報告12)では、窒息による乳児死亡例の6例のうち、5例は顔面が寝具に覆われた状態で発見されたと報告された。これらの症例報告では剖検情報等により詳細を分析されたが、発生頻度などの疫学情報を得ることができない。一方、消費者庁による広報資材には、人口動態統計の解析によって「掛け布団等の寝具が顔を覆う・首に巻き付く」事例が5年間で17件あったことが示された13)。別の人口動態統計に対する調査(参考資料)では、死亡診断書(死体検案書)に寝具の関与の言及があった乳児死亡例が年間10例程度みられた。しかし、これら死亡診断書(死体検案書)上の限定的な記載に基づく調査では、事案の発生状況などの詳細が明らかにならない。このように、乳児の窒息死のみならず国内のこどもの死亡事象について詳細を検討する必要があっても、わが国では情報源が極めて脆弱である。今後、死亡に際してその原因など詳細が記録されるありかたの探求や、これに基づいて有効な予防策が探索されるためのチャイルド・デス・レビュー(CDR)制度の整備によって、わが国のこどもの死亡の疫学に関して必要な検証が可能となる仕組みが形成されることが強く望まれる。諸外国と比較した発生頻度の差異など今後の検証は必要であるにせよ、わが国でも寝具の関与しうる乳児の窒息死が発生していることは確かであり、このような死亡態様は海外に限定したものではない。わが国においても、乳児の安全な睡眠環境の確保のあり方について、検討の必要は認められる。
上記のように乳児の安全な睡眠環境の確保をすすめるうえで、諸外国における研究を基盤とした推奨事項6)をわが国にそのまま適用可能かについては、更なる検証が望まれる。住環境等によって乳児の睡眠環境の実態が異なり乳児の睡眠関連死の発生状況が異なるとする報告7)を踏まえると、適切で効果的な啓発の展開には背景の理解が必須であり、住宅等の温度環境などわが国独自の実態を踏まえて、適切で実現可能な啓発が探索される必要がある。安全確保のためという表現によって不要な範囲にまで過度に規制することは、過度で無益な育児疲れの誘発、健全な親子関係の育成やこどもの発育への悪影響を及ぼしうる懸念もある。過度に具体的で一律的な規制表現は、保護者や保育関係者等に混乱を招く可能性があり、一部に受容されにくい表現が含まれることで、リーフレット全体のメッセージへの信頼や受容度が低下する等の懸念にもつながる。
わが国で乳児を寝かせる寝具について、複数地域の一般の保護者466人に対する質問紙調査により、「乳児用寝具に寝かせる」「大人用寝具上で大人用掛けぶとんも共有する」「大人用寝具上で別途乳児用掛けぶとんを使用する」との回答は、月齢0-2ではそれぞれ66%、13%、17%、月齢3-6では50%、21%、24%、月齢7以降では35%、32%、27%と報告された15)。ここで乳児用寝具の記述に「(乳児用)掛けぶとん」が含まれるか詳細な言及はないものの、「掛けぶとん」は乳児に対して相応の頻度で利用される寝具であることが推測される。このような生活習慣が一般的であるわが国において、乳児の窒息死の予防のため一律「掛けぶとんの使用を禁止する」方針は、現状との乖離が大きいことから国民の理解を直ちに得ることが困難で、実現性の乏しい推奨となることが懸念される。まずは理由を丁寧に解説して掛けぶとんを「使用禁止」ではなく、「使用により危険を生じた例がある」旨の注意喚起もしくは「使用しないことを推奨する」ことから開始し、その実現の程度と効果を経時的に観測して当該推奨の妥当性と有効性を確認した上で、その後に必要に応じて推奨の度合いを修正することが望まれる。この効果等の経時的な観測を実現するためにも、先述のCDR制度の確立は必須である。
また、どの年月齢のこどもに対する推奨事項かの検討も必要である。海外文献8)において、柔らかな寝具に起因する乳児の窒息について「毛布によって気道閉塞が発生した月齢5〜11の乳児のほぼ半数は、毛布に絡まっていた。この月齢の乳児は、毛布に絡まる程度には体動可能だが、自分で脱出できるほどの協調運動は獲得していない」と考察された。わが国の疫学は先述のとおり十分明らかではないが、寝具等が頭部に巻き付いた事例は月齢3-8で、寝具等が顔面を覆って(顔上に乗って)発見された事例は月齢2-13でのみ確認された(参考資料)ことからも、同様の考察をわが国に適用することに齟齬はないと考えられる。すなわち、寝具に抗する自動運動ができない新生児等、寝具が巻き付くような寝返りをしない月齢2-3程度までの乳児、あるいは1歳を超えて寝具を払い除けるだけの巧緻運動が可能になった児において、このような態様で窒息に至ることは考えにくい。このことを踏まえると、「掛けぶとんを使用しないことを推奨」するべき対象月齢を、月齢2(〜3)から月齢12(〜13)までに限定することも考慮されたい。ただし家庭等に対する推奨として、新生児期にひとたび使用開始した寝具を、一定の期間使用しないで養育し、さらに一定の時期に再度使用するという複雑なプラクティスには困難も予測される。この困難を回避する目的であれば、生後から1歳に到達するまでは一律使わないとする推奨も、否定されるべきものではない。
さらに、一般家庭以外の環境、特に適切な機器あるいは人員を配置した医療機関、保育施設や産後ケア施設等では、適切な監視(心拍呼吸の医療的な機械監視等も含む)が行われ、寝具の巻きつきや顔面への覆い被さり等が発生しそうになり、あるいはその結果として心拍呼吸の変動が観測された場合に直ちに適切な介入が可能と考えられるため、「掛けぶとんを使用しないことの推奨」の適用外とする運用も考えられる。なお産後ケア施設等での適切な睡眠環境のあり方については、『産後ケア施設における乳幼児安全対応マニュアル』16)等も参照されたい。一方で、家庭用心拍呼吸監視装置の有用性については未検証であり、家庭において同装置を設置することで寝具にかかる推奨の適用外とすることは、適切とはいえない。「これらの装置(消費者を直接の対象とした心拍数およびSpO2モニタリング機器)は、睡眠関連死を防ぐために使用されるべきではない。これらのモニターの使用は親に安心感を与えるかもしれないが、その使用によりこれらの死亡(睡眠関連死)のリスクが減少するとするデータは不足している」ことから、「家庭でモニターを使用することは、AAP(American Academy of Pediatrics;米国小児科学会)の安全な睡眠ガイドラインに従う代わりになるべきではないと家族が判断すべき」6)とするAAP推奨事項に、本学会としても賛同する。
適切な乳児の睡眠環境を啓発するうえで、「掛けぶとん」以外の寝具、住環境の整備、その他の睡眠環境についての言及に乏しいことは、内容として十分でないと言わざるを得ない。米国では寝具関連の乳児死亡も覆い被さりによる乳児死亡も成人用ベッドで多く発生しており8)、添い寝によって覆い被さりや挟み込みが直接死因となり死亡する月齢4以下の乳児が多い9)。AAPは「理想的には少なくとも最初の6ヶ月間は、乳児が両親の部屋で、両親のベッドの近くであるが乳児用に設計された別の面(surface)で寝ることが推奨される」と添い寝をしないことを推奨した6)。このことにより「SIDSのリスクを最大50%まで減少させるとのエビデンスがある」および「乳児が大人のベッドで寝ている際に起こり得る窒息、絞扼、または挟まれる事故を最も防ぐ可能性が高い」6)ことが見込まれる。ただし、その推奨においては「(調査に回答した一般の母親の)半数以上が乳児と添い寝をしていると回答した」7)との米国内の背景も考慮し、「AAPは、授乳の促進、文化的好み、またはそれが乳児にとってより良く安全であるという信念などの様々な理由から、多くの親が定期的に添い寝を選択することを理解し尊重している。しかしエビデンスに基づくと、どのような状況下でも添い寝を推奨することはできない」6)と解説する配慮が示されている。
わが国でもエコチル調査の関連報告14)では解析対象72,624名のうち76.8%が「親と共寝(In parent’s bed)」と回答し、別の報告15)でも「大人用寝具上で寝かせる」乳児は月齢により30-60%とされるなど、「添い寝」もわが国の乳児の睡眠環境において相応の頻度で行われる。しかし「添い寝」は乳児突然死230事例のうち61%で記録される10)など、乳児の窒息死への関与も懸念される。にもかかわらず、こども家庭庁のリーフレットでは「保護者が添い寝をする時は、赤ちゃんを身体や腕で圧迫しないように注意しましょう」とのみ記載され1)、添い寝の安全性に関する検討や注意喚起はない。今後より適切な睡眠環境にかかる啓発内容につき、継続的に検討される必要がある。
最後に、こども家庭庁のリーフレットには「掛けぶとんは使用せず、服装で温度調節しましょう」と小さく付則される1)が、先述のように使用禁止ではなく注意喚起を目的とする場合には、まず安全な睡眠環境が紹介された上で、ここに掛けぶとんの安全性に対する問題提起が付則されるべきものである。実効性のある推奨のためには、保温に関するより具体的な代替案が追記されることが好ましい。頭部に巻き付く、顔上で口鼻に密着して窒息の原因となる、重量等により胸郭の呼吸運動を阻害する、過度の加温をする、などのリスクが想定されない保温方法が図示されること等も好ましい。ベッド・イン・ベッドや乳児用スリーパー等は、安全性についてのエビデンスは限られており引き続き注意深い観測が望まれるものの、例示されうる代替策である17)。その上で今後、これらの代替案も含め、乳幼児の寝具における適切な安全基準等が策定されるべきである。なおこの点において、AAP推奨で「乳児に重ね着をさせることは、毛布やその他の寝具よりも望ましい。これにより、乳児を暖かく保ちつつ、毛布使用による頭部の覆いかぶさりや挟まれるリスクを減らすことが可能である。ウェアラブルブランケットも使用できる」6)と記載されることも参照のうえ、推奨される睡眠環境について分かりやすい図示も含めた適切な情報提供がなされる配慮が望まれる。
まとめ
乳児の安全な睡眠環境の整備の推進は、わが国の乳児の主要死因である窒息事故およびSIDSの予防に寄与することが期待される。本学会として、このことを啓発するリーフレットの意義は支持するものであるが、2024年度より寝具に関する推奨を改めた部分について疑義があり、以下の見解を表明した。
上記改訂は、米国内の乳児養育の背景と乳児死亡の解析をもとに策定されたAAP推奨を、わが国に展開することを意図したと推察される。わが国でも寝具の関与する乳児死亡が相応に発生していることが学術報告等で確認されるため、この意図そのものは適当といえる。その一方で、過度に具体的で一律的な規制表現は、保護者や保育関係者等に混乱を招き、リーフレット全体のメッセージへの信頼や受容度が低下する懸念がある。そのため、当該記載について以下の追記修正等を要望するものである。
現状において、一般的に広く使用されていると推察される「掛けぶとん」を一律「使用禁止」とすることは、現状との乖離が大きく実現性が乏しい。推奨の理由を丁寧に補足解説して「掛けぶとん」を「使用禁止」と受け取られないようにするとともに、実現の程度と効果を経時的に観測して妥当性と有効性を確認した後に、必要に応じて推奨の度合いやありかたを修正することが望まれる。
窒息の発生する病態を考慮し、「掛けぶとんを使用しないことを推奨」するべき対象を、月齢2(〜3)から月齢12(〜13)までに限定することが望まれる。ただし実施困難な場合に限っては、生後から1歳になるまで使わないとする推奨も否定はされない。
適切な監視(心拍呼吸の医療的な機械監視を含む)が行われ必要時に直ちに介入できる環境においては、推奨の適用外とする運用を考慮されたい。ここには、医療機関、保育施設や産後ケア施設等が該当しうるが、適切な監視のあり方については更なる検討が望ましい。家庭用モニターは代替として適切とはいえない。
乳児にとって安全な睡眠環境について、「掛けぶとん」以外の検討も今後なされるべきであり、この中には「添い寝」に関する推奨事項についても包含される。
実効性のある推奨のために、乳児の保温に関する代替案が具体的に明示されることが好ましく、ベッド・イン・ベッドや乳児用スリーパー等も例示されうる。ただしこれらも含め、乳児の寝具における安全基準の確立が急務である。
わが国において上述の推奨等の介入の妥当性を判断するためには、現状を正確に把握し疫学的な解析が行われる必要がある。このことを可能にするため、今後チャイルド・デス・レビュー制度の整備が不可欠である。
参考文献
1. こども家庭庁「寝ている赤ちゃんのいのちを守るために」.(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2fdd400-7af4-456b-b278-cd4ccd287229/b4028b54/20241015_policies_boshihoken_kenkou_sids_21.pdf 最終閲覧2024.12.15)
2. 厚生労働省.令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/gaikyouR5.pdf(最終閲覧 2024.12.9)
3. Parks SE, Erck Lambert AB, Hauck FR, Cottengim CR, Faulkner M, Shapiro-Mendoza CK. Explaining Sudden Unexpected Infant Deaths, 2011-2017. Pediatrics. 2021 May;147(5):e2020035873.
4. 厚生労働省SIDS研究班.乳幼児突然死症候群(SIDS)診断ガイドライン(第2版). https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/20c213ff-143f-404e-a922-f8db45e701ee/60d70c89/20230401_policies_boshihoken_kenkou_sids_guideline_03.pdf. (最終閲覧2024.12.9)
5. Rachel Y Moon; TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME. SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Evidence Base for 2016 Updated Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment. Pediatrics 2016 Nov;138(5):e20162940.
6. Rachel Y. Moon, Rebecca F. Carlin, Ivan Hand, THE TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME AND THE COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN; Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment. Pediatrics July 2022; 150 (1): e2022057990. 10.1542/peds.2022-057990
7. Bombard JM, Kortsmit K, Warner L, Shapiro-Mendoza CK, Cox S, Kroelinger CD, Parks SE, Dee DL, D'Angelo DV, Smith RA, Burley K, Morrow B, Olson CK, Shulman HB, Harrison L, Cottengim C, Barfield WD. Vital Signs: Trends and Disparities in Infant Safe Sleep Practices - United States, 2009-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018 Jan 12;67(1):39-46.
8. Erck Lambert AB, Parks SE, Cottengim C, Faulkner M, Hauck FR, Shapiro-Mendoza CK. Sleep-Related Infant Suffocation Deaths Attributable to Soft Bedding, Overlay, and Wedging. Pediatrics. 2019 May;143(5):e20183408.
9. Gaw CE, Chounthirath T, Midgett J, Quinlan K, Smith GA. Types of Objects in the Sleep Environment Associated With Infant Suffocation and Strangulation. Acad Pediatr. 2017 Nov-Dec;17(8):893-901.
10. Osawa M, Ueno Y, Ikeda N, Ikematsu K, Yamamoto T, Irie W, Kozawa S, Kotani H, Hamayasu H, Murase T, Shingu K, Sugimoto M, Nagao R, Kakimoto Y. Circumstances and factors of sleep-related sudden infancy deaths in Japan. PLoS One. 2020 Aug 21;15(8):e0233253.
11. 加藤 稲子, 田中 佳世,フセイン・モハメド, 大澤 資樹,青木 康博,戸苅 創.乳幼児突然死法医解剖症例における睡眠環境の検討.日本SIDS・乳幼児突然死予防学会雑誌. 2023 Dec.; 23(1): 48-50.
12. Ito E, Hitosugi M, Maruo Y, Nakamura M, Takaso M, Masumitsu A, Baba M. Availability of death review of children using death certificates and forensic autopsy results. Leg Med (Tokyo). 2023 Feb;60:102156.
13, 消費者庁webページ「0歳児の就寝時の窒息死に御注意ください!」(2016.10.24)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/161024kouhyou_1.pdf 最終閲覧2024.12.15)
14. Sugimori N, Hamazaki K, Matsumura K, Kasamatsu H, Tsuchida A, Inadera H; Japan Environment and Children’s Study Group. Association between maternal fermented food consumption and infant sleep duration: The Japan Environment and Children's Study. PLoS One. 2019 Oct 4;14(10):e0222792. doi: 10.1371/journal.pone.0222792. PMID: 31584958; PMCID: PMC6777830.
15. 加藤 稲子, フセイン・モハメド, 藤田 英寿, 細野 茂春, 戸苅 創.健康乳児の家庭内での睡眠環境の検討.日本SIDS・乳幼児突然死予防学会雑誌. 2023 Dec.; 23(1): 2-11.
16. 日本小児突然死予防医学会(旧:日本SIDS・乳幼児突然死予防学会)産後ケア施設における安全管理マニュアル作成ワーキンググループ.「産後ケア施設における乳幼児安全対策マニュアル」(2024.8.14)(http://plaza.umin.ac.jp/sids/pdf/postnatalcare.pdf 最終閲覧2025.1.21)
17. McDonnell E, Moon RY. Infant Deaths and Injuries Associated with Wearable Blankets, Swaddle Wraps, and Swaddling. J. Pediatr. 2014; 164: 1152–1156.
18. こども家庭庁webページ「乳幼児突然死症候群(SIDS)について」(2024.12.25)(https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kenkou/sids 最終閲覧2025.1.21)