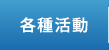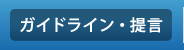ガイドライン・提言
医療的ケア児の在宅移行のための指針
2024年10月28日掲載
日本小児医療保健協議会合同委員会重症心身障害児(者)・在宅医療委員会
はじめに
救急、集中治療体制の整備、医療技術の進歩、生存率の向上により、障害や複雑な医療、ケアニーズを抱えて生活するこどもの数は増えている。わが国の統計ではいわゆる医療的ケア児数は20,000人を超え、15年間で2倍に増加している。中でも人工呼吸器を必要とするこどもは、2010年は10人に1人であったものが、2021年は4人に1人と、在宅で必要とする医療の重症度が上がっている。
今回、日本小児医療保健協議会合同委員会重症心身障害児(者)・在宅医療委員会で、在宅生活を送るうえで医療的ケアが必要になったこどもと家族が、主体的に在宅移行を行うための環境を整えるために医療者が心がけておくべきことを、指針として示すこととした。
本指針を基盤として、こどもと家族を支援する多職種(医療職・介護職・福祉職・教育職等)が、それぞれの専門性を生かし「医療的ケア児、家族のウェルビーイング(個人の権利や自己実現が保障され,身体的・精神的・社会的に良好な状態であること)の実現」という共通の目標のために、相互理解を深め連携することにつながればと願う。
1.在宅医療へ移行するための基本的条件
1)こどもへの愛着が形成されている。
2)こどもと家族が地域で生活することを希望している。
3)こどもの病状が安定している(看取りを見据えた場合を除く)。
4)家族がこどもの病状や医療行為について十分に理解している。
5)こどもと家族に加え、支援者も在宅移行の意義と目標を共有できている。
6)退院後の生活環境や、継続的な支援の体制が整っている。
7)退院後もこどもと家族が相談できる人が病院と地域の両方にいる。
8)家族と支援者との間に信頼関係が構築されている。
2.在宅移行を提案する病院の医療職が大切にすべきこと
1)こどもと家族が、様々な支援を受けながら生活することを選択できる存在であることを、医療チームで共有しましょう。
2)地域での生活に移行する際には、こどもと家族が、様々な障壁を乗り越えなければならないことを、家族とも共有しましょう。
3)こどもと家族が在宅移行を始めるためには、移行をすすめる最初の段階から多職種の人たちとの理解と連携が必要であることを、共有しましょう。
4)こどもが入院している病棟のスタッフの在宅移行に対する前向きな支援が重要であり、そのために在宅移行に関する基礎的な知識を持っておきましょう。
5)同じ病院内であっても、急性期の治療を行う部門のスタッフと、治療を引き継ぐ病棟のスタッフとの間で、こどもと家族に伝えている情報に違いがあったり、予後などについての厳しい情報を十分に伝えていなかったりしていることも少なくありません。病院内の職種間で十分な情報交換を行いましょう。
3.在宅移行を提案する際に医療職が心がけること
1)患者の支援において医療の役割が変わることとその意味の共有
治療・安全を基本とした病院モデルから、人として、こどもらしく生きる暮らしを基本とした生活モデルへの転換を理解することは、家族にとって困難な課題の一つです。医療ソーシャルワーカーなどの福祉職にも早くから支援を求めましょう。NICUでは親になる過程を支援し、PICUでは新たな親子関係をつくる過程を支援し、病棟では親が親であることを支えましょう。病院内のそれぞれの場所で、親が病気を持ったこどもを受容することを支え、地域では家族になる過程を支えましょう。
2)こどもと家族に対する現状の説明と理解の促進
在宅移行を行う際には、家族が予後も含めたこどもの病状の理解と、多くの方々からの支援の必要性を十分に理解することが必要です。その上で、医療的ケア児と家族の願いを実現させるために、すべての支援者がそれぞれの立場で行なえる支援の内容について、様々な限界がある中で努力していることを理解しようとすること,実現には時間が必要なことを理解することも必要です。
①こどもの病状について、家族が十分に理解できるように平易な言葉で説明する機会を、何度もつくりましょう。
②こどもの病状の理解において、両親間で理解に大きな差がないことを確認することも重要です。説明の際には、可能な限り両親の同席が望ましいです。
③病気、病状、発達について、今後の見通しについても、わかる範囲の中で詳しく説明しましょう。
④退院後も医療的ケアが必要であると判断できた早い時点で、保護者に理解しやすい説明を始めましょう。
⑤保護者が重篤なこどもの病状を理解し、受けとめるには長い時間が必要なこと、さまざまな葛藤があること、常に病気は良くなるとの希望を持っておられることにも配慮しましょう。
3)こどもと家族のエンパワーメント
学習と挑戦:医療的ケア児と家族は、ウェルビーイングの実現と能動的な支援のために自らが行動する必要があることを理解することが必要です。
信頼と気遣い:支援者は、医療的ケア児、または家族が持つ自ら行動できる力を信じることも必要です。同時に、彼らが他者と常に繋がっているか、悩みを抱えていないかを確認することも重要です。
それぞれのこどもの個性と家族の思い:支援者は、支援を受ける主体がこどもであること、それぞれのこどもと家族の思いが違っていてもよいことを、理解しましょう。
きょうだいに対する支援:影響を受けやすいきょうだいへの支援も忘れてはなりません。
保護者も自らの人生を考える:主な介護者に、仕事を継続する意思があれば、困難であっても、支援を継続すること、そのための相談者や支援者を得るために、介護者が自らも行動できるようにエンパワーメントすることも大切です。
4)少し立ち止まり、皆が休むことが必要な時もあります
こどもたちが安全で幸せでいられるためには、家族と介護する人が健康であり、『私』という一個人でいられる時間が持てることが大切です。
こどもも家族も疲れてしまうこともあります。今の自分たちにとって必要な支援について考える時間を持ち、支援の内容を検討し、選択することも、必要なことです。
4.退院計画の立案と提示
1)在宅生活を提示する際に検討すべき内容
①医療的ケアが必要な重症児が在宅に移行するための医学的な問題(入院中に解決できるもの、解決できないもの、今後新たに生じえる問題・課題)を整理しましょう。
②家族の抱える問題点を捉え、問題解決のために家族の力を分析しましょう。
③問題点の解決方法を検討しながら、在宅移行の可能性を検討しましょう。
④在宅で暮らしていくための支援内容(退院の際に必須なもの、必須でないもの、退院後に新たに必要となるもの)を整理しましょう。
⑤在宅で暮らしていくために必要となる具体的な病院と地域の支援者と、各々が支援できる内容を確認し、役割分担を明確にしましょう。
⑥協力、調整して行くために病院内と、地域での責任者を明確にしましょう。
⑦明確な行程と、役割分担を示した退院計画を立案し、こどもと家族の願いに沿っているか、実際に生活できる計画になっているかを家族とともに検討しましょう。
⑧在宅で行うケアの安全性、有効性、効率性、持続可能性について検討しましょう。
⑨これらの内容の検討のための、家族を含めた病院内外の多職種が参加する退院前カンファレンスの開催も検討しましょう。
2)具体的な退院計画の進め方
①早めに始めましょう(入退院支援加算の活用)
こどもが、集中治療室にいるときから、こどもと家族をよく理解した医療職が、退院計画チームと協力して家族に関わることは、家族のエンパワーメントに向けて動き出す手助けになることもあります。
②早い段階で地域の支援者にも関わっていただきましょう(介護支援等連携指導料の活用)
経験のある看護師や医療ソーシャルワーカーが、早い段階から病院内の調整、訪問看護/リハビリ、訪問診療、薬局などの地域の多職種との連携を行いながら、退院後に支援の中心となる病院外の職種とも協力してチーム形成を行いましょう。早期から、地域の保健師、相談支援専門員、行政の障害福祉課或いは担当者、子育て関連部署などの担当者にもチームに加わっていただくことで、地域の支援者もこどもと家族を知ることができ、家族の思いを共有し、一貫した支援を提供することができます。病院の看護師と訪問看護師、病院主治医と訪問診療医などが密な関係性を構築し、医療・ケアの内容を共通化する作業を行うことは、ケアの差異や偏りを最小限に抑えることにつながり、支援の質が最適化され、不必要な親のストレスが軽減されます。
退院後の訪問看護、訪問診療などが速やかに支援を開始することも視野に入れ、家族と地域の支援者とが、よく話し合って退院日を設定します。 病院内と病院外の支援者の役割を明確にしておくことは、退院後のこどもの不安定な状態や、在宅生活の継続が困難であると判断することに有効です。退院後の緊急時対応が必要となった際には、こどもを再度入院として、より良い支援について再度検討しなおすことも有効です。
③家族と支援者に具体的な在宅移行のプランを示して退院調整を実施する
(1)こどもと家族が毎日安心して暮らせる状態になっていることが重要です。
(2)退院後のサービスの利用を含め、家族が退院後の生活を具体的にイメージできる様に話し合いを進めることが必要です。そのためには、すでに在宅で生活されている医療的ケア児のご家族を紹介してもよいかもしれません。
(3)さまざまな福祉サービスを受けるための手続きや物品の購入、移動のための車いすなどの作成、自宅のリフォームなどには時間がかかることも考慮してください。
(4)こどもと家族に対して、多職種の役割を分かりやすく伝えておくことが必要です。
(5)支援者や家族の間で、各人が行うべき内容を明記した行程表(24時間スケジュール、1週間スケジュール)を共有することは重要です。退院支援を行う中で、確実に退院支援の遂行がなされているか、こどもの病状に変化はないか、保護者の気持ちの変化がないか、新たな問題が起きていないかを常に確認します。
(6)医療者をはじめとする多職種とこども・家族との良好なコミュニケーションのための場を設けること、必要であれば複数回設定することは非常に重要です。WEBを利用した情報交換でよいか、直接集まったほうが良いか、意見交換の場にこども・保護者を招くことが良いかどうかは、様々な状況を考えて個別に判断することがよいでしょう。
(7)様々な理由により病院からの退院調整が困難な時には、地域の病院や施設などの中間施設の協力を得ることも考えましょう。
(8)こどもが入院している病院と、地域のクリニック、訪問診療医、地域基幹病院とが、退院後の診療、急変時の対応、在宅物品の支給などの役割分担についてしっかりと話し合いましょう。
(9)病院での指導内容が絶対的なものでなく、こどもの成長、病状や家族も含めた生活の変化に伴って医療的ケアの内容は変化すること、変更する際には訪問診療・訪問看護を中心とした生活と医療の両方に関わる支援者との話し合いが重要であることを理解しましょう。
(10)地域への移行を行う上で、こどもと家族が必要とする医学的、心理的、社会的および精神発達面での支援について配慮しましょう。
(11)在宅移行後も、支援内容の見直しや再調整、また、家族の負担を軽くしたり、リフレッシュしたりするための、入院や、レスパイト施設との連携も必要です。
(12)こどもも家族も支援者も、孤立させないことが重要です。
(13)支援の質の向上のためには、退院後に、病院内外の同職種および多職種間の振り返りと継続した情報交換を行うことが重要です。
参考資料
具体的な在宅移行のプラン作成のための参考資料を以下に記す。
・令和3年度厚生労働省委託事業 在宅医療関連講師人材養成事業-小児を対象とした在宅医療分野-.小児在宅医療に関する人材養成講習会テキスト
https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000934620.pdf(参照:2024年10月28日)
→ 令和5年度厚生労働省委託事業 在宅医療関連講師人材養成事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39311.html(参照:2024年10月28日)
・小児在宅医療支援研究会 在宅医療に向けてのステップ
www.happy-at-home.org/5.cfm(参照:2024年10月28日)
・支援者のための子どもの在宅医療ガイドブック < 乳 幼 児 編 > 札幌市
https://www.spesapo.or.jp/posts/22294773(参照:2024年10月28日)
・NICUからの退院・地域生活移行支援 フローチャート M-Terrace
https://msserious.com/contents
・神奈川県立こども医療センター 在宅医療の手引き
https://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/828438.pdf(参照:2024年10月28日)
・令和2.3年度 小児在宅ケア検討員会報告書 日本医師会小児在宅ケア検討委員会
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20220427_4.pdf(参照:2024年10月28日)
→ 2022・2023年度 小児在宅ケア検討員会答申 日本医師会小児在宅ケア検討委員会
・令和6年度診療報酬改定の概要 【重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001252074.pdf(参照:2024年10月28日)
参考文献
1. Complex Care at home for Children(CMC) in Canada
Hospital discharge of the child with medical complexity
2. 3.04 Specialized Services: Child with Medical Complexity
J. Hosp. Med. 2020 June;15(S1): e102-e103
https://shmpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.12788/jhm.3399
3. Improving transitions in care for children with complex and medically fragile needs: mixed methods study
Curran JA, Breneol S, Vine J, et al.: BMC Pediatrics. 20:219,2020
4. Programmes to support transitions in care for children and youth with complex care needs and their families: a scoping review protocol
Doucet S, Curran JA, Breneol A, et al.: BMJ Open.10, e033978,2020
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/6/e033978.full.pdf
5. Children's Hospital Association Coordinating All Resources Effectively Award (The CARE Award). : A national three-year project to transform care delivery and payment for children with medical complexity. https//www.childrenshospitals.org/Care
6. Complex Care Has Arrived.
Simon T.D,: Hosp Pediatr. 10: 631–632, 2020
7. Discharge Communication Practices for Children with Medical Complexity: A Retrospective Chart Review:
Rush M, Herrera N, Melwani A.: Hosp Pediatr. 10: 631–632, 2020
8. Transitioning Children with Medical Complexity from Hospital to Home Health Care: Implications for Hospital-Based Clinicians:
Nageswaran, S, Sebesta MR, Golden SL.: Hosp Pediatr. 10: 631–662, 2020
作成担当
日本小児医療保健協議会合同委員会 重症心身障害児(者)・在宅医療委員会
余谷 暢之(委員長)、岩本彰太郎(副委員長)、中村 知夫、竹本 潔、
中村 和幸、渕上 達夫、臼井 秀仁、石井 光子、石渡 久子、大瀧 潮、
川村健太郎、小篠 史郎、奈倉 道明、永江 彰子、小林 拓也、三尾 仁、
小沢 浩、高田 哲、渕上 達夫、谷口 由枝、仲野 敦子、鈴木 郁子、
三浦 清邦、望月 成隆(委員)、松尾 宗明、藤枝 幹也(担当理事)
査読
日本新生児成育医学会 和田 浩 先生