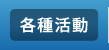各種活動
2025年3月29日
ポリオに関する注意喚起および、急性弛緩性麻痺(AFP)の届出義務の周知
日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会
要旨
- ワクチン株が変異した病原性の高いワクチン由来ポリオウイルスの伝播が先進国を含めて国際的に問題になっている。
- 日本は急性弛緩性麻痺の報告数が少なく、正しく報告してワクチン由来株などによるポリオ麻痺を否定する必要性がある。
- 全ての医師には、15歳未満の急性弛緩性麻痺症例(ギラン・バレー症候群等を含む)を速やかに保健所に届け出る義務がある。
ポリオの概要
急性灰白髄炎(ポリオ)は、ポリオウイルスが中枢神経に感染し、運動神経細胞を不可逆的に障害し、弛緩性麻痺等を生じる感染症である。主に感染者の便を介してポリオウイルスが人の口の中に入り、腸の中で増えることで感染する。まれに汚染された水や食物などからも感染する。ポリオウイルスには、3つの血清型(1, 2, 3型)がある1)。
潜伏期間は3~21日(通常は7~21日)、感染しても90~95%は不顕性感染で、4~8%は軽症であり、発熱、感冒症状や胃腸症状などが見られる。感染者の1~2%は、頭痛、嘔気、嘔吐、頸部及び背部硬直などの髄膜刺激症状を呈する。感染者の0.1~0.2%が典型的な麻痺型ポリオとなり、1~2日の風邪様症状の後、解熱に前後して急性の筋肉麻痺、特に下肢の麻痺(急性弛緩性麻痺(Acute Flaccid Paralysis:AFP))が起きることが多く、永続的な後遺症が残る可能性がある2)。急性灰白髄炎を発症すると、小児では2~5%が死亡するといわれ、成人の場合はより重症化しやすく、致死率は15~30%といわれている3)。
麻痺の進行を止めたり、麻痺を回復させたりするための治療が試みられてきたが、現在、確実な治療法はない。3つの血清型のポリオウイルスに対するワクチン接種がポリオの発症予防・流行制御のための戦略となる4)。日本では、2012年9月に、定期接種で用いられるワクチンが三価経口生ポリオワクチン(trivalent oral poliovirus vaccine: tOPV)から強毒株由来(conventional)不活化ポリオワクチン(conventional inactivated poliovirus vaccine: cIPV)に切り替えられ、11月からは世界に先駆けてワクチン株であるSabin株を不活化したSabin株由来(Sabin-derived)不活化ポリオワクチン(sIPV)とジフテリア・百日せき・破傷風混合ワクチンを混合した4種混合ワクチンDPT-sIPVが導入された(2024年度から5種混合DPT-sIPV-Hibに変更)。日本でのワクチン接種率は95%以上であることが報告されており、感染症流行予測調査における感受性調査により、2022年の時点で5歳未満における高い抗体保有率が確認されている1)。日本では、2012年に発症し2013年に診断されたワクチン株由来の麻痺症例(1例)以降、ポリオ確定症例の届出はない。
昨今の世界におけるポリオウイルス検出状況
世界保健機関(World Health Organization: WHO)は1988年に世界ポリオ根絶計画を提唱した。野生株ポリオウイルス(wild poliovirus: WPV)の3つの血清型のうち、2型WPVは 2015年9月、3型WPVは 2019年10月にそれぞれ世界ポリオ根絶認定委員会により流行終息が宣言された。2023年の時点で流行しているWPVは1型のみであり、アフガニスタンとパキスタンで継続してヒトおよび環境水から検出されており、2021~2022年にはマラウイや隣国のモザンビークで、2019年に検出されたパキスタンの株と遺伝子的に関連のあるWPV1によるAFPの症例が報告された1)。
一方、経口生ポリオワクチン(oral poliovirus vaccine: OPV)に含まれるワクチン株(Sabin株)ポリオウイルスに変異が蓄積し病原性が復帰した、伝播型(circulating)ワクチン由来ポリオウイルス(circulating vaccine derived poliovirus: cVDPV)の出現が世界的な問題となっている。2022年のcVDPVによる確定症例数は全世界で868症例と、WPVによる症例の20倍以上である。日本を含むWHO西太平洋地域(Western Pacific Region: WPR)では、2000年にWPV伝播の終息が宣言されたが、2015年にラオス、そして 2018年にパプアニューギニアにおいて1型cVDPV(cVDPV1)、2019~2020年にはフィリピンおよびマレーシアにcVDPV1およびcVDPV2による流行が発生した。WPR外(米国、英国、カナダ)でもcVDPV2の伝播が確認されている。従って、WPVが排除された地域においても、cVDPVが出現あるいは伝播するリスクが無視できない状況である。WHOは加盟国に対し、ポリオウイルスの監視および根絶状態の維持を確認する目的で、AFPサーベイランスや下水の環境水サーベイランスを実施するよう求めている。日本では環境水サーベイランスが感染症流行予測調査事業として2013年から開始されている1)。また、AFPサーベイランスは2018年5月から感染症法に基づく感染症発生動向調査として実施されている。
WHOヨーロッパ地域 では2002年6月にポリオ根絶宣言がなされた。しかし、2015年から2022年までの報告では、毎年、ヨーロッパの少なくとも1か国で病原性ポリオウイルスが検出されている5)。特に2024年9月から12月にかけて、EU(European Union)/EEA(European Economic Area)の4か国(フィンランド、ドイツ、ポーランド、スペイン)と英国において、環境水(下水)サーベイランスにてEU/EEA諸国でcVDPV2が検出された初めてのケースとして下⽔サンプルでのcVDPV2の遺伝子クラスターの検出が報告された6)。分離されたcVDPV2は、2020年7月にナイジェリアで初めて検出された系統(NIE‑ZAS‑1)に関連しており、この系統はその後、アフリカの他の21か国にも伝播し、そのうち15か国でアウトブレイクを引き起こした7)。2025年1月30日までに、EU/EEAまたは英国では、これらのcVDPV2の検出に関連するポリオのヒト症例の報告はない6)。
ポリオに関する注意喚起
日本では 2013年以降ポリオ確定症例の届出はなく、IPVによる高いワクチン接種率が維持されており、ポリオ患者の発生リスクは低いと想定される。しかし、昨今の全世界における、WPV/cVDPVの流行、検出、そしてインバウンドが増大している状況から、WPV/cVDPVの輸入・伝播のリスクは高まっており、監視体制の強化が必要である。
日本のAFPサーベイランス
AFPは、世界ポリオ根絶計画における重要な概念であり、ポリオ様麻痺、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、急性脊髄炎、Guillain-Barré(ギラン・バレー)症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins症候群等が含まれる8)。AFPの原因ウイルスとしては、ポリオウイルスの他、エンテロウイルス(EV)-A71やEV-D68(2015年、2018年にEV-D68関連AFPが日本でも多数報告)などがある。
日本では2018年5月から感染症法に基づき、感染症発生動向調査においてAFPが5類感染症全数把握疾患「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」となり、15歳未満のAFPを診断した医師には7日以内の保健所への届け出が義務付けられた(ア.15歳未満、イ.急性の弛緩性の運動麻痺症状を伴って死亡した者、又は当該症状が24時間以上消失しなかった者、ウ.明らかに感染性でない血管障害、腫瘍、外傷、代謝障害などでないこと、及び痙性麻痺でないこと、ア~ウ3つすべてを満たす症例)。これらの要件を満たせば、ギラン・バレー症候群も届け出の対象となることも忘れないで欲しい。
さらに、2021 年には届出票が改訂され、WHOのポリオ対策の観点から、AFPを認めた全症例について便検体を感染研に送付し検査を実施することになった。また、EV-D68、EV-A71等のエンテロウイルスを含めた病原体検査の重要性から、届出票に「便検体 1 回目・2 回目」「呼吸器由来検体」「血液」「髄液」(4点セット)及びその他が記載された9,10)。
WHOの世界ポリオ根絶計画の標準サーベイランスとしてのAFPサーベイランスは、その質的指標の一つとして、15歳未満の人口10万人当たり1人以上の非ポリオAFP症例報告をもって、ポリオウイルス検出に十分な感度を有するとみなされるが、現状では日本からの報告数はその目標水準に達しておらず、サーベイランスの質が担保されていないことが指摘されている11)。加えて、豊倉らの全国の小児神経専門医を対象とした調査によると、2019~2022年に145例のAFPが報告され、うち保健所への届け出対象であった137例に対し、保健所に届け出をしたと回答があったのは41例(30%)であり、AFPの届け出義務について医師の認識が十分でない可能性がある12)。「急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き 第3版」https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003_center/0008_basis/zensu_5/AFP_tebiki_202503.pdf 9)を参照の上、AFPの迅速な探知と対応のために、全ての医師に15歳未満のAFP症例は速やかに保健所に届け出る義務があることをご理解頂きたい。なお届出票は、手引き第3版9)(13頁)を参照して欲しい。
【参考文献】
- 国立感染症研究所.厚生労働省健康局結核感染症課. ポリオ 2023年現在. IASR. 44: 113-114, 2023. https://www.niid.go.jp/niid/ja/polio-m/polio-iasrtpc/12211-522t.html (参照2025-3-3)
- 外務省. ポリオに関する注意喚起. 外務省海外安全ホームページ. https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2025C004.html (参照2025-3-3)
- 厚生労働省. ポリオについて. https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/polio/polio/index.html (参照2025-3-3)
- 厚生労働省. 5種混合ワクチン. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/dpt-ipv-hib/index.html (参照2025-3-3)
- Fischer TK, Johannesen CK, Benschop KSM, et al. Poliovirus circulation in the WHO European region, 2015–2022: a review of data from WHO’s three core poliovirus surveillance systems. Lancet Reg Health Eur. 19:47:101104, 2024. doi: 10.1016/j.lanepe.2024.101104.
- European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid risk assessment-Assessing the risk to public health of multiple detections of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater in the EU/EEA. 30 January 2025. ECDC: Stockholm; 2025. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/multiple-detections-poliovirus-wastewater-eueea (参照2025-3-9)
- Namageyo-Funa A, Greene SA, Henderson E, et al. Update on Vaccine-Derived Poliovirus Outbreaks - Worldwide, January 2023-June 2024. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 73(41):909-916, 2024. doi: 10.15585/mmwr.mm7341a1.
- 厚生労働省. 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。). https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-180413.html (参照2025-3-3)
- 厚生労働科学研究費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「急性弛緩性麻痺等の神経疾患に関する網羅的病原体検索を含めた原因及び病態の究明、治療法の確立に資する臨床疫学研究」研究班. 急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き第3版.2025年3月https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003_center/0008_basis/zensu_5/AFP_tebiki_202503.pdf (参照2025-3-9)
- 厚生労働省. 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)発生届. https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-05-180413-b.pdf(参照2025-3-3)
- World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific. “Polio Bulletin 2024”. WHO Regional Office for the Western Pacific. https://iris.who.int/handle/10665/375482 (参照2025-2-17)
- 豊倉いつみ, 佐野貴子、櫻木淳一他. 急性弛緩性麻痺に関する全国実態の一次調査. 日児誌. 129(1); 44-47. 2025.