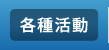各種活動
2024年10月28日掲載
日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会
現在、マイコプラズマ肺炎が流行しております。2024年の流行は、周期的な流行の年となった2016年以来8年ぶりで、2024年5月から報告数が増加しています。
そのため、「マイコプラズマ肺炎流行に対する日本小児科学会からの注意喚起」を公開しました。
マイコプラズマ肺炎流行に対する日本小児科学会からの注意喚起
2024年10月27日
日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会
全文PDF
1.マイコプラズマ肺炎の流行状況
マイコプラズマ肺炎は“肺炎マイコプラズマ”という細菌による感染症で、3~7年程度の間隔で大きな流行が起きることが報告されています。2024年の流行は、周期的な流行の年となった2016年以来8年ぶりで、5月頃から報告数が増加しています(図1)1),2)。新型コロナウイルス感染症の流行により2020~2023年は、多くの感染症の報告数が減少しましたが、“肺炎マイコプラズマ”についても同様に、免疫を持たない成人や小児が多くなっていたことが想定されます。地域や学校・クラスでの流行状況に注意しましょう。
マイコプラズマ肺炎の症状について
長引く発熱・咳などの症状がみられた際はかかりつけ医を受診しましょう。多くの人は上気道炎、気管支炎で改善しますが、一部の人は肺炎を起こし重症化することもあります。また、発疹や中耳炎を認めたり、まれに胸膜炎、心筋炎、髄膜炎・脳炎、関節炎、糸球体腎炎、溶血性貧血などの合併症が起こることもあります3)。マイコプラズマ感染症は自然治癒(self-limiting)することもありますが、肺炎に至る前の上気道炎や気管支炎の段階で検査や投薬が必要かに関しては、かかりつけ医の判断を仰ぎましょう。
“肺炎マイコプラズマ”の検査について
“肺炎マイコプラズマ”は下気道の線毛上皮細胞で増殖するため、上気道の菌量は下気道の約1%以下であり、咽頭ぬぐい液を用いたイムノクロマト法での迅速検査の感度は低く、核酸検査(PCR検査など)を実施する場合には検査結果が確定するまで数日を要します。したがって、検査で確定する前に、マイコプラズマ肺炎の患者さんとの接触歴や症状から“肺炎マイコプラズマ”による感染症を疑って、治療を開始することがあります。
マイコプラズマ肺炎の治療について
肺炎をおこすなど、抗菌薬等による治療が必要と判断された場合は、第一選択として、マクロライド系(※1)の抗菌薬が推奨されます。一方、“肺炎マイコプラズマ”のマクロライド系抗菌薬に対する耐性化が懸念されています。耐性率は地域や時期によって異なり、医師は地域の状況とお子さんの病状を勘案して薬剤を選択します。
マクロライド系抗菌薬が無効で、更に治療が必要と判断される場合は、ニューキノロン系(※2)抗菌薬あるいはテトラサイクリン系(※3)抗菌薬への変更が考慮されます。ただし、8 歳未満のお子さんには、テトラサイクリン系抗菌薬の使用は医師が必要と判断した場合に限られます。また、ニューキノロン系抗菌薬の使用はトスフロキサシン以外は小児に対して原則行われておりません。肺炎が重くなった場合には、ステロイドの全身投与も考慮されます4),5)。
※1 マクロライド系抗菌薬:クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど。
※2 ニューキノロン系抗菌薬:トスフロキサシンなど。
※3 テトラサイクリン系抗菌薬:ミノサイクリン、ドキシサイクリンなど。
マイコプラズマ感染症の予防について
感染予防のために、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ対策と同じく、手洗いを励行して、咳の症状がある場合はマスクを着用しましょう。
参考文献
1. 国立感染症研究所. 感染症発生動向調査週報(IDWR)過去10年間との比較グラフ.
https://www.niid.go.jp/niid/ja/10/2096-weeklygraph/1659-18myco.html (参照2024-10-5)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/10/2096-weeklygraph/1659-18myco.html (参照2024-10-5)
2. 国立感染症研究所. IDWR 2024年第35号<注目すべき感染症> マイコプラズマ肺炎.
https://www.niid.go.jp/niid/ja/mycoplasma-pneumonia-m/mycoplasma-pneumonia-idwrc/12871-idwrc-2435.html(参照2024-9-16)
3. Shah SS, Mycoplasma pneumoniae. In: Long SS, Pickering LK, Prober CG, eds. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases 6th Edition, Elsevier Inc. 2023; 1041-1045.e4.
4. 国立感染症研究所. マイコプラズマ肺炎とは.
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/503-mycoplasma-pneumoniae.html (参照2024-9-18)
5. 日本小児科学会. 小児肺炎マイコプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方.
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/saisin_130219_2.pdf (参照2024-9-18)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/mycoplasma-pneumonia-m/mycoplasma-pneumonia-idwrc/12871-idwrc-2435.html(参照2024-9-16)
3. Shah SS, Mycoplasma pneumoniae. In: Long SS, Pickering LK, Prober CG, eds. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases 6th Edition, Elsevier Inc. 2023; 1041-1045.e4.
4. 国立感染症研究所. マイコプラズマ肺炎とは.
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/503-mycoplasma-pneumoniae.html (参照2024-9-18)
5. 日本小児科学会. 小児肺炎マイコプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方.
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/saisin_130219_2.pdf (参照2024-9-18)