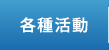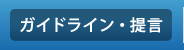ガイドライン・提言
(登録:2003.06.24)
小児脳死臓器移植はどうあるべきか
|
日本小児科学会小児脳死臓器移植検討委員会
2003年4月26日 はじめに
わが国の脳死臓器移植法は1997年7月に成立し、同年10月に発効してから5年以上が経過したが、この間に施行された臓器提供者は20数例を数えるに過ぎない.わが国の脳死臓器移植法は本人の生前の意思表示と家族の同意の両者を必要とする提供者の人権を尊重した法律であり、世界に類をみない.しかし、わが国の民法では15歳未満の小児での生前の意思表示を認めていないことから現在のところ、小児脳死臓器移植は不可能である.現行法の付則に見直しが施行後3年と記載されていることと、成人臓器では対応できない海外渡航による心臓・肺などの小児脳死臓器移植数が増加している現実から脳死臓器移植法案の見直しが検討されている.
小児脳死臓器移植に関する小児科学会
小児臓器移植について日本小児科学会あるいはその分科会が議論を開始したのは1983年、第25回日本小児神経学会(会長 鴨下重彦)であった.この時は『来るべき将来の小児脳死臓器移植問題を考えよ』と提言する内容であった.とくに、脳死臓器移植法改正案(厚生省「臓器移植の法的事項に関する研究班」による町野案)が2000年8月23日に公表されてから小児臓器移植に関する検討が熱心にされるようになった.また、小児循環器学会を中心に小児脳死心臓移植適応基準、待機患児の実態と問題点、公開シンポジウムによる啓発活動がなされてきた. |
| 年月日 | 学会 | タイトル・内容 | 発表者など |
| 1983年 |
25回日本小児神経学会 (会長 鴨下重彦) (夜間集会) |
小児脳死を考える |
座長:牧 豊 演者:竹内 一夫、 二瓶 健次、藤田 慎一 |
|
2000年 6月8日 |
第42回日本小児神経学会 (会長 岡田伸太郎) イブニングトーク |
子どもの脳死について(本文参照) |
演者:竹内 研三 (鳥取大学脳神経小児科) 阪井 裕一(国立小児病院) 宮林 郁子 |
|
2001年 3月 |
日本小児科学会 | 小児臓器移植に関するアンケート調査 |
日本小児科学会倫理委員 (詳細は日児誌105巻11号,日本小児科学会HP) |
|
2001年 5月5日 |
日本小児科学会第1回公開フォーラム |
小児の脳死臓器移植はいかにあるべきか (詳細は日児誌105巻11号,日本小児科学会HP) |
座長:中村 肇 演者:柳田 邦男 公開討論会 座長:谷澤 隆邦、仁志田博司 パネリスト: 森岡 正博 (大阪府立大学倫理学) 杉本 健郎 (関西医科大学小児科・遺族) 町野 朔 (上智大学法学部) 恒松由記子 (国立小児病院) 阪井 裕一 (国立小児病院麻酔・集中治療科) 曽根 威彦(早稲田大学法学部) 鈴木 利廣(弁護士) 田辺 功(朝日新聞論説委員) 掛江 直子 (国立精神・神経センター精神保健研究所) |
|
2002年 9月6日 |
第20回日本小児心身医学会総会シンポジウム | 子どもの脳死状態における全人医療(本文参照) |
座長:松石豊次郎、田中 英高 演者: 松石豊次郎(久留米大学) 杉本 健郎(関西医科大学) 安藤 泰至 (鳥取大学保健学科) 山口 龍彦 (高知厚生病院ホスピス) |
|
2003年 1月13日 |
日本小児科学会第2回公開フォーラム |
子供の死を考える in Kobe (詳細は日児誌107巻4号,日本小児科学会HP) |
座長:仁志田博司、谷澤 隆邦 演者: 細谷 亮太 (聖路加国際病院小児科部長) 杉本 健郎 (関西医大男山病院小児科部長) 高木 慶子 (兵庫・生と死を考える会) 額田 勲(神戸みどり病院・神戸生命倫理研究会代表) 田中 英高(主催者から) |
|
(4)日本小児循環器学会および関連学会の活動
2.学会活動 |
|
3.国際シンポジウム
4.公開シンポジウム |
|
5.要望書提出
[1] 2001年2月衆議院議長・参議院議長への要望書提出 [2] 2001年7月国会議員への説明 中山代議士.宮崎代議士、阿部代議士他 [3] 2002年3月日本小児循環器学会からの 小児心臓移植・肺移植の要望 総理大臣小泉純一郎への要望書提出 [4] 2002年2月松田班からの小児心臓移植・ 肺移植の要望 総理大臣小泉純一郎・厚生労働大臣・衆議院・ 参議院議長・生命倫理委員会会長への要望書提出 |
|
小児海外渡航心臓移植
国内での小児心臓移植例は2003年1月17日現在で心臓移植施行17例中2例である.とくに、心臓移植は生体肝・腎・肺移植とは異なり生体ドナーからの移植は不可能である.また、成人ドナーからの心臓移植はドナー・レシピエントの体重差が3倍以上となる概ね体重が20kg未満のレシピエントでは困難である. 提 言
上記の経緯と背景を踏まえ、日本小児科学会倫理委員会として小児脳死臓器移植検討委員会を設置してわが国での小児脳死臓器移植の現状と問題点の検討を重ねてきた. 文献
1) Shewmon AD. Chronic“brain death” Meta-analysis and conceptual consequences. Neurology 1998;51:1538―1545. |
(登録:2003.07.30)
小児脳死臓器移植に関するインターネットによる一般会員からのアンケート結果
先に公開フォーラム「小児の脳死臓器移植はいかにあるべきか」報告書に代議員のアンケート調査結果のまとめと「提言 小児脳死臓器移植はどうあるべきか」を掲載いたしました.
アンケート調査では、一般会員から98名と少数ですがご意見を頂いており、その詳細を公表しておりませんでしたので今回追補資料としてここに掲載いたします.
1) 経過と回答数
2001年4月上旬から6月上旬までの約2ヶ月間インターネットによるアンケートを行いました。その間4月中旬に学会誌(5月号)に最初の「お願い」を出し、5月5日の小児科学会フォーラムと仙台での学会総会にもアンケートの「お願い」をしました。結果は残念ながら約0.6%の98人の回答でした。この98人は基本的に代議員は含まれていないはずです。
代議員の文書によるアンケート回答が1ヶ月間で63%という比較的高率に対して、何故このように少数回答であったか。
アンケート回答時に打ち込みを完全に行わない限り終了できないという欠陥が指摘されましたが、やはりインターネットを駆使できる医師数が少なく、さらにアンケートに答えるという方式そのものがまだまだ普及していないことが考察されました。しかし、小児科学会員が多数入会しているメイルネットは1000人をはるかに超えていることからみると、脳死・移植そのものが身近な問題として捉えられなかったのかもしれません。国会の関係で、アンケート調査が突然何の前触れもなく実施されたことに会員の違和感があったことや、宣伝が十分に行き届かなかったことも関係しているのかもしれません。
より安価な方法ということでインターネットによるアンケートを実施したのですが、取り組み側の体制不備をお詫びします。
2) 結果
98人の回答を分析します。
[1]所属都道府県
回答の多い順に示します。大阪17、東京9、兵庫と福岡7、京都と北海道が6、神奈川5と続きました。
[2]専門別
「小児科」との記載ないし「記載なし」が多かったのですが、専門性の記載では、多い順に、神経・精神21、アレルギー・感染10、新生児9、腎臓7、循環と血液・腫瘍が5と続きました。
[3]年齢
多い順に列記します。41歳から45歳が最も多く27、 36歳から40歳が19、45歳から50歳が18、51歳から55歳が13、31歳から35歳が8、26歳から30歳が7、61歳以上が5、56歳から60歳が1でした。
[4]性別
男性73、女性25
[5]所属
臨床勤務が44、開業が34、大学研究が18でした。
[6]脳死=死を認めるか
「はい」が69、「いいえ」21、「わからない」8でした。
[7]小児科医が意見を述べる
「はい」が97、「わからない」が1でした。
[8]小児からの脳死移植の必要性
「はい」62、「いいえ」19、「わからない」17
[9]町野教授らの報告への賛否
「賛成」21、「反対」64、「わからない」13
[10]意見表明の年齢
6歳未満が26、6歳から9歳が18、10から12歳が
22、13歳以上が30
[11]今後の方策
チャイルドドナーカードが38、死の教育が62、子ども専門コーディネーター60、専門委員会が65でした。
[12]倫理委員会として継続的な専門委員会設置
「はい」が91、「いいえ」が7
質問8
要旨を順不同に列記します。
・学会としてこの問題に限らず発言していく必要あり。
・沈黙は金の時代は終わった。存在価値を示す意味でも学会として発言すべき。
・脳死基準は成人と同様とは思わない。学会は医学的、倫理的基準を確定させるべき。
・学会としてインターネットで会員のアンケートをとったことを歓迎します。
・学会が技術専門的見地からリーダシップをとるべき、ただし代表メンバーの偏見でなく広く意見をもとめるべき。
・学会誌に定期的に資料や討論内容を掲載し、外部からの批判ものせていく。
・学会としての社会的責任を果たすべきで、今回のアンケートは泥縄式であった。継続的取り組みを。
・外国で移植を受ける子どもがいることは子どもの移植を容認している。ドナーになる人の討論が必要。
・脳死を死とする宗教観が整っていない。成人でもむつかしいのに子どもにまで適応は早すぎる。
・虐待からの移植の防止が可能でしょうか。
・ドナーもレシピエントも親と独立したこどもの意志を反映するシステムが必要。
・移植の前にまず小児救急の整備だ。
・治療放棄された脳死といわれた新生児仮死児が快復した。脳死は受け入れがたい。
・臓器移植は人の命を踏み台にして生きること。倫理的に危惧がある。
・子どもの出した結論を親が受け入れられない時、主治医はどうする?
・15歳以下の小児の脳死からの移植は人権侵害である。
・ドナー側への配慮がレシピエント側の論理より優先すべき。それが出来ないときは脳死移植をするな。
・オーム真理教の子どもは自分で入信したか?子どもの学校での死の教育が必要。
・小児の自己決定という概念がもっときちんと法的に討論されるべき。
・現法の原則が妥当。15歳以下の臓器提供のための自己決定には無理がある。
・大人の思いこみで子どもの意志が無視されないような活動が必要。
・移植を前提としない脳死判定の普及が必要。
・小児専門の公的コーディネーターが必要。
・脳死としての死を認め、レシピエントの死を認めない矛盾した医療。
・15歳以下は親の判断というのは抵抗がある。
・大脳皮質がなくなっても長期生存例がある。この子をどう取り扱うかが大切。
・死の教育については。「生きること」を問いかける教育がたいせつ。
・小児への目いっぱいの延命治療がある。長期間の集中治療で疲弊した臓器が必要なのか。
・海外へ行く子どもの実態調査をすべき。その家族の声もきくべき。
・臓器移植と脳死判定は別物。
・脳死判定以前に小児の救急体制が不十分。移植を受けた子どものサポート態勢も不十分。
・子どもの親、子ども自身からもっと意見を聞くべき。
・小児の脳死移植をひろく一般に問いかける、さらに子ども自身にもアンケートをとる。
・生物学的な死と子どもの社会的存在の死は異なる。
・ドナーカードをもっていると救命すべき子どもと認められず、ドナーとして見られる危険性あり。高知の場合はすべての手だてが行われたのか。
・親の了解だけで子どもの移植が可能はさけるべき。小児科医の中でも討論も必要。
・小児の脳死は成人とは異なる。脳の可塑性もある。成人同様の取り扱いは絶対反対。
・公正な判定と移植が必要。このごろ情報公開を拒否する傾向は危険な徴候。
・小学校や中学校へ出向き、子ども達の意見を聞いたらどうだろう。
・アメリカをはじめとした海外で何故他国の患者に移植しなければならないかという討論がある。
・移植を必要としない難病の親や宗教、弁護士などと討論必要。
・脳死が本当に死なのか?小児の虐待がふえていることも気になる。
・脳死が実際存在するのか?脳波検査は実にいい加減である。脳波に頼った判定は問題がある。
3) 考察
会員数に対して、回答があまりにもすくないので、十分な比較はできないが、あえて代議員アンケート結果と比較する。
主な相違点は以下の通り。
[1]回答年齢が代議員アンケートよりも10年以上若い層であった。殆ど男性の意見に対して、1/4が女性の意見であった。
[2]専門性や所属は大きな差はないが、近畿地方都市部の回答が多かった。
[3]脳死を死とみとめるかは、70%が容認であり、代議員の80%と差があり、同様に小児の脳死からの移植の必要性の質問でも代議員が73%に対して63%と同じ差がでた。これは同じ小児科医でも年齢により意見が異なる可能性を示唆し、代議員層より若い層の方がより脳死による臓器提供に慎重である可能性も伺えた。
[4]町野案への意見でも、反対が65%で、代議員の50%とは大きな差が見られた。賛成は21%対34%であった。
[5]意見表明可能年齢でも、代議員の結果は13歳以上から低年齢の選択肢へ順に減少したが、アンケート結果は13歳以上と6歳未満がほぼ同率であり、6歳未満で可能とする回答が多くみられた。
質問2と質問7の今後の学会での検討や意見を述べたりする事への支持は両者とも90%を超えていた。この点は、代議員アンケート結果と同様であり、今後の小児科学会での取り組みを期待するものであった。