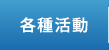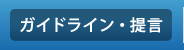ガイドライン・提言
(登録:2008.3.31)
わが国の社会への「保育環境の整備に関する」提言
日本小児科学会次世代育成プロジェクト委員会提言
日本小児科学会次世代育成プロジェクト委員会
育児は本来親が行うのが基本であり、それを社会が支えるしくみが必要です。しかしながら、核家族化の進行、男女共同参画の推進、子育てに対する親の意識の変化などにより、低年齢児の保育施設での保育が今強く求められています。一方、核家族化した現在の家庭では他者との関わりの機会が減少しており、保育施設では現代の家庭環境では体験できない他者との関わりの機会が増え、子どもが自律性と社会性を学ぶ場になりうることも事実です。さらに、保育施設は親にとっても職場以外の人間関係を構築できる機会となりえます。しかし、このような社会状況の中で重要なことはできるだけ子どもと親が家庭にて接する時間を増やすことです。この目的を達成するために、子育てを担う保護者への、社会・国からの積極的な支援が必要です。
- 本来保育は保護者の責任であり楽しみでもあります。また、子育てを通じて、子育てをする側が人間的に成熟することも重要な事実です。但し、子育てをする保護者を社会や国がこれまで以上に積極的に支援することが必要です。
- 乳幼児期に温かい人間関係を構築することがその後の人生に大きな影響を与えます。幼い子どもたちの育児はその意味で大変に重要な仕事であることを保護者だけでなく社会全体が認識しなくてはなりません。
- 様々な家族構成の事情や社会へのニーズに対応するため、保育施設には以下の4~10に述べる事項が望まれるべきです。しかしながら子育て、保育の原点に立つとき、子育てを保護者が延長保育、夜間保育、病児保育、病後児保育を利用しなくても済む労働環境の整備や経済的支援について社会をあげて改善することが必要です。
- 保育施設には小児保健に関する豊富な経験と知識を持つ看護師を導入することが望まれます。さらに、0歳児が入園する保育施設の園医には子どもの病気と保健に関する知識と経験を有する小児科医が就任することが望まれます。
- 保育施設には保育についての豊かな知識と経験を持つ保育士をこれまで以上に配備することが必要です。
- 保育施設には6か月までの乳児を他の児から分けて養育することのできる、静かな環境の部屋を確保することが必要です。とりわけ乳児には日中の睡眠時間を十分に確保できる環境整備が不可欠です。
- 子どもが栄養学的にも適切な、健康的で愛情にあふれた食事をとること、和やかで楽しい雰囲気のもとで保育者と共に食事をすること、子どもが食事のマナーを修得・実践できる環境を整備することなど、食育の観点から見た総合的な対応が重要です。
- 子どもが病気の時は、保護者やそれに代わる親族が病気の子どもをみるのが原則です。しかしながら、病児保育・病後児保育の社会的必要性は今後ますます高くなることが予想され、それらの整備が必要とされます。一方、子どもが病気になった時に保護者が仕事を休んでも、保護者の職場での立場が弱くなったり損になったりしないように、子育てをおこなう保護者への支援制度が整備されていることも必要です。また、家庭内での育児の負担が母親だけに重くならないよう、夫や親族の積極的な協力も必要です。
- 今後、長時間保育、休日保育、一時保育などの整備が予定されています。このような保育システムの充実は現代の社会にとって意義がありますが、それを利用する保護者のマナーの育成が同時に必要です。
- 保育時間の長時間化は子どもの成育にとって必ずしも望ましくない面があります。特に、乳幼児にとって温かな母子関係が構築されることがその後の人格形成に不可欠なためです。従って、母親の代わりとして、保育施設では特定の保育士と乳幼児との間の愛情にあふれる人間関係を作るため保育施設では担当制を取ることが望ましいと考えます。また、保育を利用する側も、保育の長時間化には問題がある点を認識すべきです。
- 保育所の機能を地域に浸透させ、家庭で子育てをしている保護者をも支援する施設にすることも重要です。
- 障害児保育は障害児のみならず健常児の成長や発達のために重要な社会資源です。社会全体でこれを支え、さらに広めるためにも人的資源の充実が必要です。