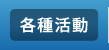各種活動
(登録:2005.06.27)
国による日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて
―日本小児科学会コメント
日本脳炎とその流行状況について
日本脳炎は国内では1960年代前半まで年間2000-4000人の報告数がありましたが、日本脳炎ワクチンが導入された1970年代より激減し、1992年からは年間10人以下の報告となっています(感染症法第4類全数把握疾患)。その原因として、日本脳炎ワクチンの普及による免疫保有者の増加の他に、環境要因の変化として多くの人にとって日本脳炎ウイルスを保有するブタを刺した蚊に刺される機会が少なくなった、つまり感染源との接触の機会が減少したことなども要因のひとつと考えられます。
日本脳炎を発症した場合、積極的な治療法はなく、発症者の20-40%が死亡、生存者の 45-70% には精神神経学的後遺症が残り、ことに小児では重度の障害を残しやすい、とされています。一方日本脳炎ウイルスに感染しても日本脳炎を発症する人は少なく(100-1000人に1人)、また人から人へ感染することはありません。
現状のように患者数が少なくなっている状態でかつ多くの人の間で免疫がある程度維持されていれば、感染者数や発症者数が今すぐ容易に増大することはないであろうと予測されていますが、それはこのような要因を考慮してのこと考えられます。
自然界の中で動物がウイルスを保有し蚊がそれを媒介するため、環境からウイルスを駆逐することは極めて困難です。また予防接種が不活化ワクチンであるため、免疫の持続は長期間に及ぶものではありません。したがって痘瘡(天然痘)やポリオ、麻疹などと異なり、たとえどんなにワクチンの普及に努めても、疾患やウイルスの根絶を目標にすることはほとんど不可能と考えられます。
水田耕作・蚊(コガタアカイエカ)の存在・ブタ飼育という共通性を持ったアジア地域では、日本脳炎は広範囲に常在する重大疾患とみなされています(急性脳炎の実体は不明の地域が多い)。
日本脳炎ウイルスの生息状況
国内に於いて患者数は減少しましたが、ウイルスの感染を受けているブタは北海道・東北地方を除いては数多く、ことに西日本以南ではブタの感染状況は調査対象の80-90%に達している地域が多いことが明らかになっています。また、ヒトの間で日本脳炎として発病はしていないもののウイルスの感染を受けている不顕性感染者は少なくとも数パーセント存在することも明らかになっています。
したがって日本脳炎は国内においては依然、潜在的な危険性を持つ感染症であり、何もしないままであれば感染者そして発症者がやがて増加する可能性をはらんだ、いぜん油断することは出来ない感染症であると考えられます。
日本脳炎ワクチン
現在使用されている日本脳炎ワクチンは我が国で開発され、WHOにより唯一その安全性と効果が承認されているワクチンで、アジアで広く使用されているものです(中国の一部では生ワクチンが国内で使用されている)。日本脳炎ワクチンは、マウスの脳内に日本脳炎ウイルスを接種しこれを採取、精製しワクチンとしたものですが、現在のワクチン液の中には、マウス脳成分としてのタンパク質は検出限界以下となっています。しかし、マウス脳を原材料としているところから、その微少な成分による脳アレルギー反応すなわち脳細胞に脱髄が極めて稀に生ずるかもしれないという理論的リスクが払拭されないままとなっています。この理論的リスクを回避するために開発されたのが、マウス脳細胞を使用しない組織培養細胞(ベロ細胞)由来の日本脳炎ワクチンです。ベロ細胞由来の日本脳炎ワクチンは、これまでの成績では安全性と効果に関してマウス脳由来のワクチンと同等またはそれ以上とされ、国内ワクチンメーカーにより製造承認の申請が行われていると報道されています。
急性散在性脳脊髄炎(Acute disseminated encephalomyelitis: ADEM)について
急性散在性脳脊髄炎(Acute disseminated encephalomyelitis: ADEM)とは、感染症、あるいはワクチン接種を誘因として自己免疫性の機序で発症するのではないかと考えられている、小児に稀に生じる原因不明の炎症性脱随性疾患です。診断後はステロイドによる治療が行われますが、その予後は比較的良好とされています。
最近の全国レベルでの調査(宮崎、多屋、岡部らによる中間報告)では、我が国に於けるADEMの発症頻度は年間50-60例程度、15歳以下の小児人口100万人あたり年間2-3人の発生であると推計されています。宮崎らによる94-95, 99-01, 01-02年に於けるAND(小児急性神経系疾患)調査では、国内約10地域より59例のADEM(ほとんどは原因不明)の報告があり、発症のピークは6歳前後で、全治19%、軽快66%で死亡例はなかったと報告されています。
日本脳炎ワクチン関連との可能性が疑われワクチン接種後の健康被害救済対象となったADEM例
日本脳炎ワクチンは、マウス脳を原材料とするその製造方法から稀ながらADEMを生ずる理論的リスクがある、といわれているところから、我が国では潜伏期間と考えられるワクチン接種後10-14日(4-21日)後に神経症状が現れ著しい健康被害が生じたとして救済申請がなされた場合には、厚生労働省予防接種健康被害認定審査会において審査が行われ「予防接種と疾病との因果関係について肯定する明確な根拠はないが通常の医学的見地によれれば肯定する論拠がある」にあたるとして、被害救済の対象となっています。
日本脳炎ワクチン関連で生じた可能性が否定できないとして健康被害が認定された例は平成元年度以降これまでに今回の症例(山梨県)を含めて14例(うち重症例5例)であり、年間およそ1例以下の認定となります。ただし、この2年間で救済を求めた件数は、6件に増加しています。
なお、被害救済とは別に、医師等による副反応報告(報告であり、詳細についての医学的評価はされてない。予防接種後の有害事象を広く報告する制度)がありますが、平成6年度からこれまでに21例の報告があります。平成15年度は6例、平成16年度には3例の報告であり、これも近年平均数を上回る傾向にあります。
厚生労働省の今回の「国による日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて」は、新たな科学的根拠が判明したわけではありませんが、理論的リスクとしての疑いが払拭されない中で重症例が出現したということで、より慎重を期するという行政判断から、次世代の日本脳炎ワクチン(ベロ細胞由来:マウス脳由来による神経アレルギーの発現があるかもしれないという理論的リスクは回避される)に切り替えられるまでの間、一時的な措置として積極的な勧奨(ほとんどすべての子供に接種を呼びかける)を控えたものと説明されています。
今後の対応に関する小児科学会のコメント
日本脳炎は潜在的危険性を持つ重症感染症であることには変わりがなく、日本にとって長い目でみて今後も必要なワクチンであると考えられます。しかし、ヒトからヒトへと感染が次々と広がる可能性はないこと、都会生活者が多いという現在の生活形態から多くの子供たちにとって感染のリスクが高いわけではないこと、急性脳炎としての顕性発症率は低いこと、などから、稀な副反応を危惧するのであれば、短期間(1年前後程度)広汎な接種はすすめずに、次世代ワクチンの出現を待ってもよいのではないだろうかと考えます。ただし、蚊に刺されないよう注意をすることはこれまで以上に行うべきです。なお日本脳炎ウイルスの媒介蚊であるコガタアカイエカは、夕方以降ヒトを刺す習性があります。
一方感染リスクの高い生活環境にある子どもである場合(ブタにおける日本脳炎ウイルス感染が高い地域での郊外生活、あるいはそのような地域での長期滞在、アジア地域への長期滞在{ことに雨期}など)には、稀な理論的リスクより感染リスクによる健康障害の可能性が高くなるので、小児科医として個別に接種をすすめるという考え方は妥当であると考えられます。この場合、従来の日本脳炎ワクチン定期接種年齢の範囲であれば、従来通り定期接種として扱われます。それ以外の年齢では、これも従来通り任意接種の扱いです。
今回の国の決定は、「国による積極的な勧奨は控える」というものであり、日本脳炎を予防接種法による定期接種対象疾患から外したわけではありません。したがってこれまでの定期接種対象となる年齢の小児に対してinformed consentを得た上での日本脳炎ワクチンの接種は、費用の負担、万一の場合の事故の救済などについて、従来通り定期接種としてみなされることは国からの説明でも明らかです。したがって、定期接種としての年齢にある接種希望者に対しては、予防接種の実施主体である自治体は、これに対応すべき責務があり、適切な方法によって予防接種を行う限りは個々の接種医師の責任ではないことも従来通りであると考えられます。