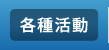各種活動
(登録:2007.06.05)
麻疹対策に関する見解と要望
日本小児科学会予防接種感染対策委員会
平成19年5月末現在、関東地方を中心に小児科年齢を若干超えた年齢層での麻疹の流行により、休講(校)、学校行事の中止、順延などが続いております。
日本小児科学会では、平成18年7月5日「麻疹サーベイランス強化(全数把握)に関する要望」を、厚生労働省に提出しております。
そこには、
「平成18年4月1日より法改正により麻疹、風疹の定期予防接種として、MRワクチンによる2回接種法の導入を行い、追って政令附則第2条の削除を行ったなどは、我が国における麻疹及び風疹対策の強化として大いに歓迎すべきことであることは、これまでにも表明してきたところです。
しかしこれで一気に疾患の排除(elimination)にまですすむわけではなく、残された感受性者の間での散発的発生、ワクチン接種者の間での免疫獲得不十分あるいは減衰者(secondary vaccine failureなど)における集団発生、そしてこれらによる感染の循環が当面続くことは、これまでにも海外において経験されているところです。したがってわが国においてはその対応策としてまずサーベイランスを強化し、発生状況を正しく把握し、適切に速やかに感染拡大を予防するための対策をとることが重要であると思われます。」
と明記してあり、まさに現在の若者の間での麻疹の流行状況は「残された感受性者の間での散発的発生、ワクチン接種者の間での免疫獲得不十分あるいは減衰者(secondary vaccine failureなど)における集団発生」であります。ここで今後の対策強化を行わないと「感染の循環が当面続く」ことになり、麻疹による犠牲者の発生、社会的混乱が数年ごとに繰り返され、さらには我が国も加盟国として属するWHO西太平洋地域(WPRO)による2012年までの麻疹排除(elimination)に、わが国は遠く離れることになってしまいます。
これからとるべき対策として
- 麻疹に対する正確な状況把握と対応策を検討し、わが国における麻疹排除の戦略を策定するための公的な麻疹対策委員会を厚生労働省内に速やかに設立する。
- 麻疹サーベイランスについて、これまでの定点報告から全数報告性に切り替え、対策に必要な正確な情報を速やかに把握する
- 残された感受性者、すなわち定期接種該当年齢から外れるワクチン未接種者未罹患者、ワクチン接種者の間での免疫獲得不十分あるいは減衰者(primary、およびsecondary vaccine failure)における集団発生の予防を行なう。具体的には、定期接種麻疹第二期の徹底とともに小学校、中学校、高等学校、大学など入学時等において学校当局あるいは教育委員会、文部科学省などの理解と協力を得て、麻疹感受性者の把握と該当者への麻疹ワクチン接種の積極的な勧奨を行うシステムを国として構築する。
- 定期第1期接種に関しては、さらなる高い接種率(95%以上)を目標とする。
- このために必要なワクチンの確保を行なう
- 麻疹対策と風疹対策は共通であり、また風疹感受性者に対する対策も合わせて行なうことによって先天性風疹症候群対策も行なえるところから、この時に使用するワクチンは原則的にはMRワクチンとする。
ことなどが早急に行われることを、日本小児科学会として強く要望します。
なおわが国においてはMRワクチンあるいは麻疹単抗原ワクチンは、国内における通常の定期接種を十分賄うことを目的に生産され、また検査も個別あるいは小集団での診断ないしスクリーニングを想定して検査システムの構築が行なわれているところから、現状のような流行下において緊急ワクチン接種及び緊急スクリーニング検査に支障を来しつつあります。
ワクチン接種にあたっては出来るだけ接種対象者を絞りワクチン接種量全体を抑制するためにはスクリーニングは有効ですが、接種そのものに抗体測定は不要で、抗体保有者へのワクチン接種は医学的には問題ありません。
現状のように一時的に限られた量のワクチンを接種する場合には、最優先されるべきは、麻疹ウイルス感染によって重篤化することが容易に想定される未接種未罹患者、および第1期定期接種対象者(1歳代)であると考えられます。1回ワクチン接種の経験があるsecondary vaccine failureの可能性のある者については、感染発症した場合には感染源にはなり得るもののその多くは軽症に終わるので、ワクチンが再び市場に多く出回るようになってから対象にすることも考慮すべき段階であるかと思われます。
以上