 |
日本小児科学会雑誌 目次 |
第108巻 第1号/平成16年1月1日
Vol.108, No.1, January 2004
バックナンバーはこちら
|
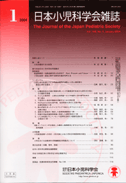 |
|
|

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 心臓超音波法の諸計測値を用いた小児腹膜透析患者の左室形状分類とその臨床的意義 |
| ■著者 |
東京女子医科大学腎臓病総合医療センター小児科1)
千葉県こども病院腎臓科2),同 循環器科3)
永渕 弘之1) 秋岡 祐子2) 青墳 裕之3) 大田 敏之1)
服部 元史1) 白髪 宏司1) 伊藤 克己1) |
| ■キーワード |
| 左室拡張末期内径,左室拡張末期後壁厚,体液量過剰,高血圧,腹膜透析 |
| ■要旨 |
小児腹膜透析(PD)患者の左室形状を心臓超音波法(UCG)の諸計測値を用いて分類し,体液量過剰や左室ポンプ機能の評価におけるUCGの有用性について検討した.
小児PD患者27例に対し,UCGを施行し,Mモード左室短軸像で拡張末期内径(LVDd)および拡張末期後壁厚(LVPWTd)から左室形状を分類した.LVDd>115%Nでは全例高血圧を呈し,除水強化により全例降圧したことから,高血圧の主因は体液量過剰(前負荷増大)であることが推察された.LVPWTd>125%NではPD期間が有意に長く,長期にわたる左室負荷増大(不十分な体液量コントロール,尿毒症など)に対し,左室壁肥厚を起こしたと考えられた.LVDdの上昇は循環血液量の増大,LVPWTdの上昇は持続性の左室負荷増大を示唆し,小児PD患者におけるUCGを用いた左室形状評価は左室負荷状態の把握に有用であると思われた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 子どもの精神的・心理社会的問題への大学病院小児科専門外来の取り組み |
| ■著者 |
神戸大学大学院医学系研究科成育医学講座小児科学1),市立川西病院小児科2),兵庫県立こども病院脳神経内科3),神戸大学発達科学部4),甲南女子大学人間科学部5)
永瀬 裕朗1) 北山 真次1) 亀田 愛樹2) 相馬 収3) 岡田 由香4) 稲垣 由子5) 中村 肇1) |
| ■キーワード |
| 発達行動小児科学,精神障害,心身症,発達障害,外来統計 |
| ■要旨 |
| 小児科を受診する精神的・心理社会的問題をもった子どもの実態を把握するために2001年1月から12月までの1年間に神戸大学医学部附属病院小児科発達行動外来を受診した101例の初診患者を対象とし,臨床的特徴について検討した.当外来受診患者は小学校低学年を中心とした男児と中学生を中心とした女児が多くを占めた.紹介元では半数が医療機関からの紹介で来院しており,その殆どは小児科からの紹介であった.主訴と診断では,発達障害と行動の問題や身体症状を訴える小児心身症の2群が主な対象となっていた.発達障害は男児に多く,小児心身症の中で身体症状,精神症状を示す症例には女児が多かった.精神的・心理社会的問題を対象とした外来であるが,初診時に感情・気分の問題といった精神的な主訴を訴える子どもは殆どいなかった.また精神病の診断がついた症例も認めなかった.発達障害,小児心身症とも年齢が高くなると,より多彩な心因性の症状をもった患者が受診しており,診療に際して注意を要することが示唆された.約半数の症例が短期間のうちに終了となっていたが,長期予後に関しては今後の検討が必要であると考えられた. |
|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 不登校の心身症的側面を評価するための問診票 |
| ■著者 |
国立療養所医王病院小児科1)
国立精神神経センター国府台病院精神科2)
国立療養所再春荘病院小児科3)
大阪医科大学小児科4)
金沢大学大学院医学研究科環境生態医学5)
梶原 荘平1) 齋藤万比古2) 樋口 重典3)
田中 英高4) 長瀬 博文5) |
| ■キーワード |
| 心身症,問診票,不登校 |
| ■要旨 |
| 身体症状を強く訴える不登校には,心身症によるもの,またDSM-IVによるところの神経症性疾患としての不安障害,気分障害(双極性障害を除く),身体表現性障害,適応障害によるもの,およびその両方の特徴を合わせ持つものがあり,これらを簡便に鑑別することは特にプライマリ・ケアにおいて治療を組み立てるうえで重要である.そこで,不登校の心身症的側面を簡便に評価するための問診票を作成し,心身症としての不登校の診断基準の作成を試みた.結果,心身相関で心理的ストレスが改善されると身体症状が改善されるという項目と,身体症状の特徴として1)学校を休むと症状が軽減する2)身体症状が再発・再燃を繰り返す3)気にかかっていることを言われたりすると症状が増悪する4)1日のうちでも身体症状の程度が変化する5)身体的訴えが2つ以上にわたる6)日によって身体症状が次から次へと変化するが時々以上みられるという6項目を合わせた7項目のうち5項目以上認められる場合,心身症としての不登校である可能性が高いと考えられた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| Methylphenidate投与後,成長障害を認めた注意欠陥/多動性障害の1例 |
| ■著者 |
横浜南共済病院小児科
成 相 昭 吉 |
| ■キーワード |
| 注意欠陥/多動性障害,methylphenidate,成長障害,成長ホルモン分泌不全,dopamine |
| ■要旨 |
6歳9カ月よりmethylphenidate(MPH)を内服開始した後に,身長増加速度が5.4cm/年から3.7cm/年に減衰した注意欠陥/多動性障害(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder,ADHD)の8歳7カ月男児について内分泌学的検査を行った.
GH分泌刺激試験でのGH頂値は,dopamine receptorを介してGRF分泌が促進されるインスリン負荷,clonidine負荷ではそれぞれ4.0ng/ml,9.3ng/mlと低反応を示した.しかし,ソマトスタチン分泌を抑制するarginine負荷では17ng/mlと正常反応,GRF receptorを直接刺激するGRF負荷では76.1ng/mlと過剰反応を示した.
以上より,本症例ではMPH連用により視床下部―下垂体GH分泌系の中でdopamine受容体を介する系が抑制され,部分的GH分泌不全を招いたために成長障害を生じたのではないかと推察された. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 胸水貯留を伴ったマイコプラズマ肺炎に対するステロイド治療の検討 |
| ■著者 |
米沢市立病院小児科1),山形大学医学部小児科2),山形市立病院済生館小児科3)
岡田 昌彦1) 野呂 瑞佳1)2) 本間 信夫1)
秋葉 香1) 池田 博行1)3) 清水 行敏1) |
| ■キーワード |
| マイコプラズマ肺炎,胸水貯留,IL-6,IL-10,ステロイド |
| ■要旨 |
| 今回,我々は胸水貯留を伴ったマイコプラズマ肺炎に対してステロイド治療を行い著明な症状の改善が得られた4症例を経験した.患者は発熱および咳嗽を主訴に入院した5歳から11歳の男児であった.いずれもクリンダマイシンやミノサクリンに反応せず,CRPやLDHの上昇あるいは胸水貯留等の臨床症状の増悪がみられた.全例で第6ないし10発熱病日に寒冷凝集反応の上昇が,一方,症例3は発熱から7日目また症例4では10日目にマイコプラズマPHA抗体の上昇がみられマイコプラズマ肺炎と診断された.第7ないし11発熱病日にステロイドを投与したが,2,3日後に解熱し症状および検査値の改善が得られた.症例3についてサイトカインの推移を検討したところ,急性期にIL-6,IL-10,sIL-2Rの上昇がみられた.本疾患の病態には感染の他に炎症および免疫反応が関与していると考えられ,ステロイドを併用する治療的意義が示唆された. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 扁桃炎の経過中に発症した扁桃周囲膿瘍の1例 |
| ■著者 |
滋賀医科大学小児科
宗村 純平 藤野 英俊 大野 雅樹 竹内 義博 |
| ■キーワード |
| 扁桃周囲膿瘍,小児 |
| ■要旨 |
| 扁桃周囲膿瘍は扁桃皮膜と咽頭収縮筋の間の疎性結合組織に炎症が波及して膿瘍を形成する疾患で小児の報告例は稀である.今回我々は扁桃周囲膿瘍の小児例を経験したので報告する.症例は6歳男児.発熱,咽頭痛を主訴に近医を受診したところ扁桃炎と診断され,抗生物質を処方された.症状は速やかに改善したため,抗生物質の内服を家族が中断したところ再び発熱,咽頭痛が出現した.近医を再診し扁桃および軟口蓋の著明な腫脹を指摘され,当科紹介入院となった.造影CT検査にて扁桃周囲膿瘍と診断し,全身麻酔下にて切開排膿を行った.扁桃炎は日常においてよく遭遇する疾患であるが,Streptococcus pyogenesの続発症や扁桃炎合併症である扁桃周囲膿瘍を予防する目的で,抗生剤による治療方針を家族に理解してもらうことが必要であると考えられる. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 同種末梢血幹細胞移植後に発症した膜性腎症の1例 |
| ■著者 |
大阪府立母子保健総合医療センター腎・代謝科,同 血液腫瘍科*
山藤 陽子 山本 勝輔 井上 雅美*
河 敬世* 里村 憲一 |
| ■キーワード |
| 膜性腎症,同種幹細胞移植,慢性GVHD |
| ■要旨 |
| 同種幹細胞移植後の慢性GVHD(graft-versus-host disease;移植片対宿主病)の関与が考えられた膜性腎症の1例を経験した.尿所見は他の慢性GVHD症状の増悪と関連して出現し,それらの治療をするに伴って改善した.慢性GVHDに伴う膜性腎症は,慢性GVHDによって産生された自己抗体が免疫複合体となり糸球体へ沈着していると考えられているが,我々の症例では調べた範囲では自己抗体は検出されなかった.慢性GVHDの標的臓器は皮膚,肝,口腔,眼,消化管,肺など多岐にわたるが,腎臓や中枢神経がその標的となるのは稀とされていた.しかし近年,幹細胞移植が確立された治療となり,症例も蓄積され長期生存例が増加していることから,腎症の報告が見られている.幹細胞移植後の血尿,蛋白尿の原因として慢性GVHDに伴う膜性腎症を考慮すべきであると考えられた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| L1CAM遺伝子にナンセンス変異を認めたX連鎖性遺伝性水頭症の1例 |
| ■著者 |
虎の門病院小児科1)
多摩南部地域病院小児科2)
吉野谷友香1) 能勢 哲2) 岡野 幸子1)
吉澤 敦子1) 横谷 進1) |
| ■キーワード |
| X連鎖性遺伝性水頭症,L1CAM遺伝子,ナンセンス変異 |
| ■要旨 |
| 胎生期から管理を行い,10歳の現在まで経過観察しているX連鎖性遺伝性水頭症の1男児例を報告する.母方親戚の男子のうち少なくとも9名に先天性水頭症を認め,大部分が早期死亡している.在胎27週より脳室拡大とその進行を認めたため35週1日,帝王切開により出生した.日齢8に脳室腹腔シャント術を施行した.下肢に対麻痺があり,全身の筋緊張が低い.発語を認めず著しい精神運動発達遅滞があるが,発達が徐々にみられる.本症例は,末梢血リンパ球DNA解析でL1CAM遺伝子のExon8に従来報告されていない870(C→A)のナンセンス変異を認め,著しく短縮した変異蛋白の生成による機能喪失変異と推定された.本症例の経緯を通して,重症先天性水頭症に対する胎児期からの適切な管理は,生命予後とおそらく神経学的予後を改善すると考えられた.こうした情報は本疾患の遺伝相談においても有益と考えられる. |

|
| 【短報】 |
| ■題名 |
| B型インフルエンザを発症した重症心身障害児に対するオセルタミビルの使用経験 |
| ■著者 |
沖縄整肢療護園小児科
大城 聡 平安 京美 仲田 行克 |
| ■キーワード |
| B型インフルエンザ,重症心身障害児(者),オセルタミビル |
| ■要旨 |
| B型インフルエンザと診断した重症心身障害児(以下,重症児)8例にオセルタミビルを投与し,その有効性について検討した.発熱から解熱するまでの全発熱時間の平均は75±28.4時間(平均±SD)であった.全例発熱後24時間以内にオセルタミビルを投与されたが,48時間以内に解熱したのは3例のみで,投与後発熱時間の平均は67.3±26.5時間(平均±SD)であった.これまでの報告と比較して,全発熱時間およびオセルタミビル投与後発熱時間のいずれもが長くなる傾向を示した.これらの結果からは,重症児のB型インフルエンザではオセルタミビルの有効性が低下している可能性も示唆されることから,今後多数例での検討が必要と思われた. |

|
| 【小児医療】 |
| ■題名 |
| 小児救急医療への対応―2交代制による小児科24時間体制の確立― |
| ■著者 |
徳島赤十字病院小児科
吉田 哲也 中津 忠則 漆原 真樹 東田 好広
高橋 昭良 松浦 里 高岡 正明 |
| ■キーワード |
| 小児救急医療,小児科24時間体制,当直制 |
| ■要旨 |
| 2002年4月から当院では,小児科24時間体制を確立し,全ての小児救急医療に小児科医が対応できるようにした.小児科24時間体制は,7名の小児科医で対応している.小児科医の勤務体制は,当直制ではなく,2交代制で,昼間は8時間,夜間でも16時間の勤務とし,次の勤務者に引き継いでいる.小児科医は,平日昼間は3名,休日昼間は2名,夜間は1名で対応している.当院は,検査部・放射線部・薬剤部なども24時間体制で対応している.さらに,すべての小児救急患者を受け入れており,小児科入院ベッドもいつも確保できている.体制としては,ほぼ理想に近いものと考えている.小児科24時間体制を開始した2002年4月から,小児科時間外受診患者数は大幅に増加(3.8倍)した.2003年になって,2002年をさらに上回っている.時間外入院患者数の推移も同様の傾向にあった.小児救急医療を確立し,質を上げるためには,一定の医療圏に1箇所,小児救急医療の中核病院を設定し,必要な人と物を集中して投入し,地域の小児救急患者すべてに,対応できるようにすべきと思われる. |

|
| バックナンバーに戻る
|

