 |
日本小児科学会雑誌 目次 |
第107巻 第3号/平成15年3月1日
Vol.107, No.3, March 2003
バックナンバーはこちら
|
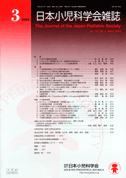 |
|
|

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 小児気管支喘息に対する非発作期のタッピング療法 |
| ■著者 |
富士市立中央病院小児科1),
国立成育医療センター.免疫アレルギー研究部2),
東京慈恵会医科大学小児科3)
| 瀬川 孝昭1)3) |
吉成 聡1)3) |
秋山 直枝1)3) |
今井 祐之1)3) |
| 千葉 博胤1)3) |
斉藤 博久2) |
衛藤 義勝3) |
|
|
| ■キーワード |
| 体位排痰法,喀痰,肺理学療法,気道のクリーニング,気管支喘息 |
| ■要旨 |
喘息発作時における体位排痰法(以後タッピング療法とする)は広く行われているが,非発作期のタッピング療法の効果についての報告は,現在までのところない.
われわれは1996年より気管支喘息に対し感染症からの喘息発作を予防するために,発作期だけではなく非発作期にもタッピング療法を施行してきた.今回その効果について統計学的に検討し,さらに非発作期のタッピング療法を行っている母親達からその効果についてのアンケート調査を行った.
1.ケトチフェン+テオフィリンを服用中の喘息児15名に非発作期のタッピング療法を加え,施行前後の発作数,感染症に伴った喘息発作数,救急外来受診回数,入院回数等の検討を行い,タッピング療法施行前後で有意差(p<0.05)を認めた.
2.当科外来を受診中の喘息児で,中発作よりケトチフェン+テオフィリンが開始された50名について,非発作期のタッピング療法施行群25名とタッピング療法未施行群25名の2群に分け1年間の喘息発作数,肺炎併発数,救急外来受診回数,入院回数について検討を行い有意差(p<0.05)を認めた.
3.平成13年11月26日から12月17日までの4週間に当科外来を受診した喘息児121名の母親達より,非発作期のタッピング療法の効果に関するアンケート調査を行った.母親達は,その効果を非常に高く評価し鋭く患児の変化を観察,実施に関していろいろ工夫していることがわかった. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 小児RSウイルス感染症の臨床像の検討 |
| ■著者 |
国家公務員共済組合連合会幌南病院小児科
| 鹿野 高明 |
大島淳二郎 |
岡田 善郎 |
| 中島 泰志 |
高橋 豊 |
|
|
| ■キーワード |
| RSウイルス,小児,酸素投与,抗菌剤 |
| ■要旨 |
最近2年間に入院した5歳以下のRSウイルス感染症の215症例を生後3カ月未満,3カ月〜6カ月未満,6カ月〜1歳未満,1歳〜2歳未満,2歳〜5歳の5群に分け,臨床症状,検査所見,酸素投与の有無,入院期間について検討した.臨床症状では,年齢が小さいほど発熱(≧38.0℃)する症例が少なかった(3カ月未満群26%対6カ月〜5歳例88%).喘鳴は若年齢に多く認めた(3カ月未満群87%対2歳〜5歳群69%).検査成績では,低年齢ほどCRP値が低くかった(3カ月未満群0.58mg/dl対2歳〜5歳2.28mg/dl).若い年齢ほど入院期間は長く酸素投与も多かった(3カ月未満群6.7日と22%対6カ月〜5歳例4.36日と3.3%).
これらの所見は年齢により臨床像に著明な差があることを示している.また3カ月未満児では発熱なくCRP低値にもかかわらず,呼吸困難を呈することがある. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 中枢神経症状を伴う手足口病の臨床的検討 |
| ■著者 |
神鋼加古川病院小児科1),兵庫県立淡路病院小児科2),
兵庫県立健康環境科学研究センター感染症部3)
| 吉田 茂1) |
藍 祥子1) |
今井 恵介1) |
| 三舛信一郎1) |
箙 ひとみ2) |
藤本 嗣人3) |
|
| ■キーワード |
| エンテロウイルス71,手足口病,無菌性髄膜炎,脳幹脳炎,弛緩性麻痺 |
| ■要旨 |
2000年夏,兵庫県加古川市で中枢神経合併症を伴う手足口病が多発した.症例は28例(性比1:1,年齢:1カ月〜8歳,中央値3.5歳).合併症の内訳は,無菌性髄膜炎のみの症例が15例(軽症例),小脳失調,Myoclonic jerks,弛緩性麻痺,けいれん,脳幹脳炎のいずれかを伴った症例が13例(重症例)であった.重症例は3歳未満に多く,有熱期間が長く,中枢神経症状発現が早く,髄液細胞比率がより多核球優位であった.26例は後遺症なく治癒したが,1例に右上肢弛緩性麻痺が残存し,脳幹脳炎の1例が死亡した.血清抗体価,RT-PCR,ウイルス分離により,71%の症例でエンテロウイルス71感染が証明された.
コクサッキーA16(CA16)抗体の有無で見ると,CA16抗体(+)群は(−)群に比べ平均1.5日有熱期間が短かく,CA16抗体が交差免疫として有熱期間の短縮に寄与している可能性が示唆された. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 超低出生体重児の上気道常在細菌叢と口腔内母乳塗布のMRSA保菌への影響 |
| ■著者 |
長野県立こども病院新生児科1),信州大学医学部小児科2)
鈴木 昭子1)2) 中村 友彦1) 小宮山 淳2) 田村 正徳1) |
| ■キーワード |
| 超低出生体重児,メチシリン耐性黄色ぶどう球菌,常在細菌叢 |
| ■要旨 |
| 超低出生体重児の上気道における常在細菌叢とMRSA保菌の関係を明らかにする目的で,超低出生体重児98人のうち日齢7までに上気道の常在細菌を獲得しなかった児47名を対照群として,獲得した児51名の臨床的背景,日齢40まで施行した隔週の上気道定期培養(鼻咽頭・気管内培養)によるMRSA非保菌率の推移について後方視的に検討した.常在細菌を獲得した群は,獲得しなかった群に比較して有意にその後のMRSA非保菌率が高く(p<0.01),常在細菌叢の確立がMRSA保菌阻止に重要な役割を果たしていると思われた.常在細菌を獲得した群の臨床的背景では生後3日以内に口腔内母乳塗布された症例が有意に多かった(p<0.05).生後3日以内に口腔内母乳塗布された群(33名)は,されなかった群(65名)に比較してMRSA非保菌率が有意に高く(p<0.01),MRSA保菌防止策として生後早期の口腔内母乳塗布が有用である可能性が示唆された. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 急性回腸末端炎の臨床的検討―急性虫垂炎との比較― |
| ■著者 |
福井県済生会病院小児科
片山 啓太 加藤 英治 |
| ■キーワード |
| 急性回腸末端炎,急性虫垂炎,腹部超音波検査,エルシニア菌 |
| ■要旨 |
小児の急性回腸末端炎の患者26名の臨床的特徴を急性虫垂炎の患者15名と比較して検討した.
急性回腸末端炎では発熱,右下腹部痛,嘔吐など急性虫垂炎と同様の症状があり,腹部の理学的所見でも鑑別は困難であった.下痢は急性回腸末端炎で有意に多く,起炎菌としてエルシニア菌,カンピロバクター菌が多くみられた.腹部超音波検査では,回腸末端の壁の肥厚や回盲部リンパ節腫脹など特徴的な所見がみられ,鑑別に有用であった.しかしながら非典型例もしばしば認め,両者の鑑別には他の画像検査も合わせ,不要な手術を避けるためにも総合的な判断が必要である. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 大豆油を含む成分栄養剤で症状が悪化した慢性下痢症の2例 |
| ■著者 |
静岡県立こども病院感染免疫アレルギー科
岡藤 郁夫 木村 光明 吉田 隆實
|
| ■キーワード |
| 大豆アレルギー,遅延型アレルギー,エレンタールP,慢性下痢症,パッチテスト |
| ■要旨 |
小児用成分栄養剤であるエレンタールP®は,慢性下痢症の治療にしばしば用いられる.今回われわれは慢性下痢症による低栄養状態を改善する目的でエレンタールP®を使用したが下痢が改善せず,むしろ悪化した2症例を経験した.エレンタールP®は脂質として大豆油を使用しており,大豆油には微量の大豆蛋白が含まれている.そこで大豆アレルギーの可能性を考慮し,大豆に対するアレルギー検査を行ったところ,両者ともに特異的IgE抗体は陰性であったが,パッチテストと豆腐負荷試験が陽性であった.
以上よりこれらの症例では大豆に対する遅延型アレルギーがあり,そのためエレンタールP®摂取により下痢が誘発されたものと考えた.エレンタールP®の使用にあたっては大豆アレルギーに対する注意が必要である. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 多発性空洞を伴う広範囲肺非定型抗酸菌症の1例 |
| ■著者 |
豊橋市民病院小児科
| 安藤 直樹 |
服部 哲夫 |
金原 有里 |
村田 浩章 |
竹内 幸 |
| 長崎 理香 |
伊藤 剛 |
藤田 直也 |
柴田麻千子 |
大林 幹尚 |
| 白谷 尚之 |
小山 典久 |
鈴木 賀巳 |
|
|
|
| ■キーワード |
| 小児,肺非定型抗酸菌感染症,肺非結核性抗酸菌感染症,Mycobacterium avium感染症 |
| ■要旨 |
| 右中下肺の空洞形成病変と左肺の瀰漫性粒状影を認めた肺非定型抗酸菌症の10歳女児例を経験した.右肺の空洞が多発性で巨大であることから将来的に外科的治療を要する可能性が考えられたが,まずはアメリカ胸部疾患学会の勧告に従いリファンピシン,エタンブトール,クラリスロマイシンの三者併用療法を開始した.治療2カ月後には小空洞の消失がみられ,5カ月後には左肺病変の消失,巨大空洞内滲出液の消失が確認された.基礎疾患を有しない小児の一次感染型肺非定型抗酸菌感染症は極めて稀で,文献検索上,本邦では過去に三例の報告が見られるにすぎない.稀少例である今回の症例の臨床経過を報告するとともに,今後の治療法について最近の成人の指針を参考に考察した. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 完全房室ブロックによる心室停止を起こし緊急ペーシングにより救命しえた急性心筋炎の1例 |
| ■著者 |
市立豊中病院小児科
| 川上 展弘 |
黒飛 俊二 |
稲田菜穂子 |
本田 敦子 |
| 松岡 太郎 |
藤田 博 |
原 達幸 |
永井利三郎 |
|
| ■キーワード |
| 完全右脚ブロック,心筋炎,心室停止,ペーシング |
| ■要旨 |
| 心筋炎は心筋に炎症性病変を来した結果,一過性あるいは慢性に心筋細胞障害に至る疾患であり,ウィルスなどによる感染から引き起こされる感染性心筋炎が代表的である.今回,我々は,入院時血液検査上CKの上昇を認めるも,心臓超音波検査で良好な収縮を保ち,安静にて様子観察していたところ,翌日に心室停止を起こし緊急ペーシングにて救命し得たコクサッキーB型心筋炎の一例を経験した.患児の入院時の心電図では,完全右脚ブロック,胸部誘導でのSTの非特異的上昇を認めていた.伝導障害を合併する心筋炎は房室ブロックや完全房室ブロックによる心室停止を引き起こす危険性があり慎重な経過観察が必要である. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 横紋筋融解症で発症した極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症の5歳男児例 |
| ■著者 |
松戸市立病院小児医療センター小児内科1),千葉県こども病院代謝科2),
福井医科大学看護学科3),島根医科大学小児科4)
| 津留 智彦1) |
朴 仁三1) |
平本 龍吾1) |
奥村 恵子1) |
| 上瀧 邦雄1) |
小森 功夫1) |
星 まり1) |
林 龍哉1) |
| 高柳 正樹2) |
重松 陽介3) |
山口 清次4) |
|
|
| ■キーワード |
| 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症,横紋筋融解症,筋型,脂肪酸β酸化,脂肪酸代謝 |
| ■要旨 |
極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症筋型の5歳男児例を経験した.発症は5歳8カ月で,発熱と項部痛のため髄膜炎の疑いで紹介され入院した.血清CPK,ミオグロビンの著増と尿所見から横紋筋融解症と診断した.呼吸筋の障害から急性呼吸不全を呈し人工呼吸管理を計10日間施行した.16病日に横紋筋融解症が再発したため基礎疾患の存在を疑い検索した.横紋筋融解症再発時の血清アシルカルニチン分析により,極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症が疑われ,EBウイルス株化リンパ芽球の酵素活性測定で診断が確定した.
極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症は幼児期にも筋型として発症する例があり,筋肉痛や横紋筋融解症を繰り返す場合の鑑別診断のひとつとして認識する必要がある. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 睡眠障害に対してtizanidineが著効したAngelman症候群の1例 |
| ■著者 |
北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター小児科1),
現 旭川医科大学小児科2)
| 田中 肇1) |
角谷 諭美1)2) |
福田 郁江1) |
| 宮本 晶恵1) |
岡 隆治1) |
長 和彦1) |
|
| ■キーワード |
| 睡眠障害,Angelman症候群,tizanidine,筋緊張亢進 |
| ■要旨 |
症例は2歳男児.特記すべき家族歴,既往歴なし.在胎週数39週5日,3,360gで仮死なく出生.8カ月時に発達の遅れに気づかれ,1歳3カ月時に北海道立旭川肢体不自由児総合療育センターに精査入院,FISH検査にてAngelman症候群と診断された.
1歳6カ月頃より頻回の夜間中途覚醒と入眠困難が出現し,1歳9カ月時よりmelatoninの内服を開始.一時的に改善が見られたが2歳過ぎより筋緊張亢進に伴う睡眠障害が再燃した.抗痙縮薬であるtizanidineを1日2回(昼,夜)投与したところ,定時の入眠が可能となり,また朝まで睡眠が持続する日も多く認められるようになった.
tizanidineの睡眠障害に対する効果は,それ自体の睡眠誘発効果に加えて,筋緊張亢進の改善による覚醒刺激の減少も強く関与していると考えられた. |
|
| バックナンバーに戻る

|

