 |
日本小児科学会雑誌 目次 |
第107巻 第12号/平成15年12月1日
Vol.107, No.12, December 2003
バックナンバーはこちら
|
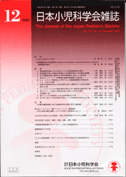 |
|
|

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 福島県相馬地区におけるRSウイルス感染症罹患率の推定 |
| ■著者 |
公立相馬総合病院小児科1),福島県立医科大学医学部小児科2)
片寄 雅彦1) 細矢 光亮2) 大西 周子1)
佐藤 敬1) 川崎 幸彦2) 鈴木 仁2) |
| ■キーワード |
| RSウイルス,下気道感染症,罹患率,医療費 |
| ■要旨 |
| 今回,私たちは福島県相馬地区におけるRSウイルス(以下RSV)感染症罹患率と入院率を推定し,また入院治療に要した医療費を算出した.その結果,1)RSVの下気道感染により3歳未満の小児の少なくとも27.5%が治療を要すること,2)RSV感染症により3歳未満の小児の少なくとも13.5%が入院加療を要すること,3)RSV感染症による入院では,平均入院期間が6.1日,医療費は1人当たり平均約17万円,人口約5万人の地区において年間約1,000万円を要することが明らかになった.RSVは乳幼児期における極めて重要な感染症であることが再確認された.また医療費の算定はワクチンや抗ウイルス剤の開発を考えた場合の基礎資料として重要であると思われた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 患者調査を用いた傷病分類別および診療科別の小児の推計患者数 |
| ■著者 |
自治医科大学公衆衛生学
上原 里程 大木いずみ 尾島 俊之 中村 好一 |
| ■キーワード |
| 患者調査,推計患者数,小児科,疾病頻度 |
| ■要旨 |
| 目的:国が実施している患者調査のデータを用いて,日本における小児の疾病頻度を明らかにすること.方法:平成11年患者調査の推計患者数を用いて,傷病分類(第10回修正国際疾病分類)別の0〜14歳の推計小児患者数を算出した.また,小児科に受診した推計患者数を外来,入院別および病院,一般診療所別に算出した.これらの推計患者数を平成8年の推計値と比較した.さらに,医師・歯科医師・薬剤師調査のデータを併用して,診療科別に小児患者の受診割合と医師1人あたりの小児患者数を算出した.結果:0〜14歳の外来受診推計患者数は「呼吸器系の疾患」が34万1千人と最多であった.小児科に受診した推計外来患者数は,平成8年との比較で「健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用」と「皮膚および皮下組織の疾患」で増加していた.診療科別の小児患者受診割合は「小児科」が47%,「耳鼻いんこう科」が15%であった.平成5年からの年次推移では,「皮膚科」を受診する割合が増加していた.「小児科」の医師1人あたりの小児患者数は22.8人であったが,年次推移の観察ではその数は減少していた.結論:最近の日本における小児の疾病頻度は,呼吸器系の疾患が圧倒的に多いものの,皮膚の疾患を有する患者数や保健サービスを利用する患者数の増加が特徴である. |
|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| BCG接種後高熱と結核疹を認め冠動脈瘤を合併した1乳児例 |
| ■著者 |
田辺中央病院小児科1),京都府立医科大学大学院医学研究科発達循環病態学2),京都府立医科大学大学院医学研究科小児発達医学3),兵庫教育大学障害児教育講座4)
上田 育代1)3) 坂田 耕一2) 村田美由紀1)4) 石丸 庸介1)石丸 尚子1) 浜岡 建城2) 杉本 徹3) |
| ■キーワード |
| BCG,結核疹,冠動脈瘤,川崎病,血管炎 |
| ■要旨 |
6カ月女児,BCG接種1カ月後に発熱と左上腕BCG接種部位の発赤と腫脹に加え,全身性の結核疹を認めた.臨床経過と病理所見よりBCG接種後の壊疽性丘疹状結核疹と診断した.イソニアジドの投与で結核疹の新生は止まったが,発熱は持続し,第22病日の心エコー検査で冠動脈瘤を認めた.川崎病の治療に準じて,フルルビプロフェンの投与を開始したところ解熱し,冠動脈瘤も次第に縮小した.
BCG接種後の全身性結核疹はまれに認められるが,冠動脈瘤を合併した報告はこれまでにない.本例ではBCG接種が誘因となり,結核疹に加え,川崎病類似の病態が引き起こされ,その結果冠動脈瘤を合併したのではないかと推測した.川崎病血管炎及び冠動脈障害の病因を考える上で貴重な症例である. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 弱毒生ポリオワクチン接種後の弛緩性単麻痺の1男児例 |
| ■著者 |
佐賀大学医学部小児科1),酒井小児科内科医院2)
石井 清久1) 松尾 宗明1) 市丸 智浩1)
酒井 良2) 濱崎 雄平1) |
| ■キーワード |
| ポリオワクチン,ワクチン関連麻痺,VAPP,compatible case |
| ■要旨 |
我々はウイルスの特定には至らなかったが,2回目の経口ポリオワクチン(OPV)接種3週間後に無菌性髄膜炎を発症し,その後胸腰髄の右側脊髄前角部を責任病巣とする下肢の急性弛緩性麻痺(Acute Flaccid Paralysis:AFP)を認めた1歳男児例を経験した.現在,日本で投与しているOPVは製造コストが安く,高い腸管粘膜免疫が得られるが,約400万例に1例の確率でワクチン関連麻痺(VAPP)が報告されるなど問題点があるため,先進国においては不活化ワクチン(IPV)を導入する方向にある.
VAPPの問題はOPVを使用しつづける限り続くと考えられ,日本においても早急にOPV単独投与に替わる,より安全でかつ有効なワクチン接種の確立が期待される. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| エンドトキシン吸着療法が有効であった細菌性髄膜炎/敗血症性ショックの1乳児例 |
| ■著者 |
市立砺波総合病院小児科1),金沢大学医学部保健学科2),金沢大学医学部附属病院小児科3)
藤田 修平1) 住田 亮1) 榎木 恵子1)
嶋 大二郎1) 谷内江昭宏2) 小泉 晶一3) |
| ■キーワード |
| 化膿性髄膜炎,b型インフルエンザ菌,エンドトキシン吸着療法,内因性大麻 |
| ■要旨 |
| 敗血症性ショックを伴った細菌性髄膜炎の乳児に対し,polymyxin-B固相化カラムを用いたエンドトキシン吸着療法(以下PMX)を施行し良好な結果を得たので報告する.症例は1歳男児,b型インフルエンザ菌による細菌性髄膜炎のため当科入院.血圧低下,意識障害を伴い,DIC,代謝性アシドーシスにより全身状態はきわめて不良でありエンドトキシンショックに陥っていると判断された.抗炎症治療,昇圧剤の投与,抗DIC治療などにもかかわらず一般状態が増悪するため,速やかなエンドトキシン除去ならびに高サイトカイン血症の是正が必要と判断し,PMXを施行した.PMX施行直後より血圧上昇,尿量増加など循環動態の著しい改善が認められた.臨床所見と異なり,PMX施行前後の血中エンドトキシン値はほとんど変化がなかった.さらに,PMX施行直後における種々の炎症性サイトカイン濃度は高値であり,アナンダマイドを代表とする内因性大麻の濃度も施行後数時間は高値を維持した.エンドトキシンショックは致死率の高い救急疾患であり,迅速な病態評価と効果的な治療の導入が要求される.本症例の経験から,PMXによる速やかな循環動態の改善は,高サイトカイン血症の改善や内因性大麻の除去によるだけではなく,多様な機序を介している可能性が示唆された.一方,乳幼児であっても循環動態の改善しないエンドトキシンショック症例では,時期を逸せずPMX治療を試みるべきであると考える. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 抗肺炎球菌特異的IgG2抗体低値を認めた膿胸を伴った肺炎球菌性肺炎の1例 |
| ■著者 |
昭和大学医学部小児科
斉藤多賀子 三浦 克志 今井 孝成
辻 祐一郎 小田島安平 飯倉 洋治 |
| ■キーワード |
| 肺炎球菌,膿胸,抗肺炎球菌特異的IgG2抗体(抗PnIgG2抗体),肺炎球菌ワクチン |
| ■要旨 |
| 症例は3歳9カ月男児.発熱,咳嗽,胸痛を主訴に当院紹介入院した.胸部レントゲン,CT像にて膿性胸腔内浸出液貯留を認め,胸水培養での肺炎球菌の検出より,膿胸を合併した肺炎球菌性肺炎と診断した.抗菌薬の投与と持続胸腔ドレナージにて軽快した.重症化した要因を病原体側と宿主側から検討した.病原体の要因としては,ペニシリン結合蛋白遺伝子のpbp1aとpbp2xの変異を認めるPISPであった.宿主側の要因としては免疫学的検査において抗肺炎球菌特異的IgG2抗体(以下,抗PnIgG2抗体)の低下を認めた.肺炎球菌による重症化する症例には,病原体および宿主の免疫学的検討が重要であり,抗PnIgG2抗体の検討も必要であると考えられた.また,肺炎球菌ワクチンの接種にて,抗PnIgG2抗体の有意な上昇を認め,再発は認めていないことから,抗PnIgG2抗体低値で肺炎球菌による重症例には肺炎球菌感染症の再発や重症化への予防のために肺炎球菌ワクチンを考慮すべきと考えられた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| ムンプスウイルスの不顕性感染が認められた急性肝炎重症型の1例 |
| ■著者 |
獨協医科大学小児科1),防衛医科大学校小児科2)
松永 貴之1) 黒澤 秀光1) 坪井 龍生1) 萩澤 進1)佐藤 雄也1) 大和田葉子1) 杉田 憲一1) 乾 あやの2)藤澤 知雄2) 江口 光興1) |
| ■キーワード |
| ムンプスウイルス,急性肝炎重症型,血小板減少,白血球減少,可溶性インターロイキン2受容体 |
| ■要旨 |
| 小児期における急性肝炎や劇症肝炎の大部分は原因が特定されない.一方,ムンプスウイルス感染症は唾液腺の有痛性腫脹を主症状とする全身性ウイルス感染症であるが,高度の肝機能障害や造血障害を合併することはまれである.我々は急性肝炎重症型に血小板減少と白血球減少を合併した4歳男児において,発症時にムンプスウイルスの不顕性感染が存在することが血清学的に証明された症例を経験した.本症例では発症時,可溶性インターロイキン2受容体が高値を示したが,その低下とともに肝機能と血球減少が改善したことより,本症の病態にTリンパ球系免疫機構の活性化や高サイトカイン血症が関与していた可能性が示唆された. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 高ガラクトース血症と肺高血圧症を合併した乳児多発性血管腫の1例 |
| ■著者 |
福島県立医科大学医学部小児科学講座
星野 玲子 桃井 伸緒 小田 慎一
鈴木 英樹 小林 智幸 鈴木 仁 |
| ■キーワード |
| 高ガラクトース血症,肺高血圧症,多発性血管腫,インターフェロン |
| ■要旨 |
高ガラクトース血症と肺高血圧症を合併した多発性血管腫の1乳児例を経験した.患児は出生時より全身の皮膚に多発性の苺状血管腫と心房中隔欠損症を認め,新生児マススクリーニングでは,軽度のガラクトース値の上昇がみられた.その後,心不全症状が出現したため,精査目的に生後3カ月時に当科に入院した.
画像検査で,肺と肝臓に複数の血管腫と,門脈―下大静脈シャント所見を得,また心臓カテーテル検査では著明な肺高血圧の所見を認めた.以上より,皮膚,肺,肝に生じた多発性血管腫と診断した.合併した高ガラクトース血症には門脈―下大静脈シャントの関与が,また,肺高血圧症の病態には,門脈―下大静脈シャントと肺内血管腫の関与が考えられた.
血管腫に対し,インターフェロンαを投与し著効を得たが,その作用機序は明確で無く,今後さらなる検討が必要である. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| BKウイルスの初感染による出血性膀胱炎の1例 |
| ■著者 |
新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻内部環境医学講座小児科学分野
長谷川博也 鈴木 俊明 平石 哲也 |
| ■キーワード |
| BKウイルス,出血性膀胱炎,PCR法,尿細胞診 |
| ■要旨 |
| 症例は生来健康な4歳男児.肉眼的血尿と頻尿,排尿時痛を主訴として入院した.尿細胞診でウイルス感染が疑われる異型細胞を認め,PCR法による検索で,尿中のBKウイルスDNAが検出されたことから,BKウイルス感染による出血性膀胱炎と診断した.健常人に対するBKウイルスの病原性は一般的に知られていないが,健常小児における出血性膀胱炎の原因としてBKウイルス感染も鑑別すべきであり,症状の遷延する症例においては,積極的に検査を行うことが必要と考えられた.BKウイルスの感染を証明するためには,尿細胞診とPCR法によるウイルスDNAの検出が有用と思われた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 肝不全に進行し生体肝移植で救命しえた特発性新生児肝炎の1例 |
| ■著者 |
帯広厚生病院小児科1),
北海道大学大学院医学研究科病態制御学専攻生殖発達医学講座小児科学分野2)
佐藤 智信1) 竹崎俊一郎1) 鈴木 大介1) 木田 和宏1)植竹 公明1) 提嶋 俊一1) 小杉山清隆2) 窪田 満2) |
| ■キーワード |
| 特発性新生児肝炎,巨細胞性肝炎,肝不全,生体肝移植 |
| ■要旨 |
| 肝生検により新生児肝炎(巨細胞性肝炎)と診断し内科的治療で経過をみていたが,生後6カ月で肝不全へ進展した男児例を経験した.症例は遷延性黄疸の精査のため当科に入院した生後2カ月の男児である.T-Bil 22.7 mg/dl,D-Bil 14.5 mg/dl,AST 1,098 IU/l,ALT 841 IU/l,γ-GTP 174 IU/lと高度の肝機能障害を認めた.胆道閉鎖は否定的で,ウイルス学的検索・アミノ酸分析でも特記すべき異常を認めなかった.生後4カ月時に施行した肝生検では典型的な巨細胞性肝炎の像を呈していた.しかし以後の内科的治療に反応せず,生後6カ月の時点で次第に肝不全へ移行し,母親をドナーとする生体肝移植術が施行された.新生児肝炎は予後良好とされる原因不明の肝内胆汁うっ滞症だが,本症例のような重症例の報告も散見される.肝不全が進行した場合は,時期を逸せず肝移植に踏み切ることが児の救命において重要と思われた. |

|
| 【短報】 |
| ■題名 |
| 小児脳死臓器移植における被虐待児の処遇に関する諸問題 |
| ■著者 |
大阪医科大学小児科学教室1),清恵会病院小児科2),大阪労災病院小児科3),友紘会病院小児科4),中町赤十字病院小児科5),枚方市民病院小児科6),八尾徳州会病院小児科7),国立成育医療センター研究所成育社会医学研究部8)
田中 英高1) 新田 雅彦2) 竹中 義人3) 永井 章4)山口 仁5) 河上 千尋6) 神原 雪子7) 金 泰子1)玉井 浩1) 谷村 雅子8) |
| ■キーワード |
| 児童虐待,頭部外傷,脳死臓器移植,小児科医,倫理問題 |
| ■要旨 |
| 虐待による頭部外傷性の脳死の頻度は低くなく,虐待の事実確認は大変に難しい上に,倫理上の理由から臓器提供には問題が多い.そこで虐待脳死小児における臓器提供の処遇に関する諸問題について,小児科医,専門医を対象に調査を行った.その結果,回答者の多くは小児頭部外傷の約3割程度が虐待による可能性があり,虐待をほぼ完全に否定するには,2週間〜1カ月以上が必要であると考えていた.また虐待脳死例では,事実確認のための証拠として,ならびに倫理的・心理社会的理由から,臓器摘出は不適切と考えていた.被虐待児を数多く含む小児脳死例における臓器移植にが問題点が多い. |

|
| バックナンバーに戻る
|

