 |
日本小児科学会雑誌 目次 |
第106巻 第7号/平成14年7月1日
Vol.106, No.7, July 2002
バックナンバーはこちら
|
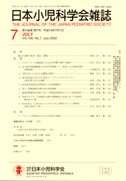 |
|
|

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| テオフィリンが脳血流におよぼす影響に関する検討 |
| ■著者 |
日本大学医学部小児科学教室
|
| ■キーワード |
| テオフィリン,気管支喘息,脳血流,経頭蓋骨的超音波ドップラー(TCD),Pulsatility Index(P.I.値),テオフィリン関連痙攣 |
| ■要旨 |
テオフィリンが脳血流におよぼす影響について検討した.対象は,テオフィリンで治療中の患児41例とテオフィリン非使用の健常児31例である.方法は経頭蓋的脳血流測定装置を用いて中大脳動脈と前大脳動脈の脳血流波形を検出し,Pulsatility Index(P.I. 値)によって脳血流量を評価した.テオフィリン使用群のP.I. 値は対照群に比べ有意に高値を示し,かつテオフィリン血中濃度とP.I. 値の間には有意な正の相関が認められた.テオフィリン静注前後でP.I.値は有意に上昇した.テオフィリン関連痙攣児ではP.I. 値は非痙攣群に比べて高値を示し,全例1.0以上であった.
これらの結果からテオフィリンは臨床的使用量で血中濃度依存性に脳血流量を減少させる可能性があり,痙攣児では減少量が大きいことが推察された.6歳未満の児にテオフィリンを投与する場合,テオフィリン血中濃度を至適血中濃度に維持するのみならずP.I. 値を1.0以下に保ち,脳血流量を維持することが痙攣予防に役立つと考える. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 先天性甲状腺機能低下症児の甲状腺エコー所見による病型分類と治療経過 |
| ■著者 |
東北大学医学部小児科
| 小島加奈子 |
勝島由利子 |
藤原 幾磨 |
| 小川 英伸 |
大浦 敏博 |
飯沼 一宇 |
|
| ■キーワード |
| 先天性甲状腺機能低下症,超音波検査,病型分類 |
| ■要旨 |
| マススクリーニングで発見され,初診時TSH 100μIU/ml以上にてクレチン症として治療を開始した10例(現在2.7〜6.2歳)を,甲状腺がエコー上正常な位置に明らかに認められた4例(正所性群)と,認められなかった6例(非正所性群)に分類し,初診時の検査所見および治療経過について比較検討した.初診時の甲状腺機能は両群で同等に低下しており,l-T4初期投与量にも差はみられなかったが,非正所性群では経過中TSHの上昇に伴い投与量の増量を要したのに対し,正所性群では投与量を増量したものはなく,2例は治療中止後もeuthyroidを保っていた.現在のl-T4投与量は正所性群で明らかに少なかった.また,非正所性群にはTSHの正常化に100日以上を要した例があった.クレチン症における甲状腺エコー検査は診断とともに治療経過の予測にも有用であり,今後病型別の治療方針も検討されるべきと考えられた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 当院NICUにおける分離菌の推移 |
| ■著者 |
自治医科大学臨床検査医学1),自治医科大学総合周産期母子医療センター新生児集中治療部2)
| 横田 京子1) |
渋谷 泰寛1) |
伊東 紘一1) |
| 本間 洋子2) |
桃井真里子2) |
|
|
| ■キーワード |
| NICU,細菌感染,耐性菌,腸球菌 |
| ■要旨 |
| 1993年から2000年までの8年間に,自治医科大学附属病院NICUから提出された各種培養検体から分離された細菌について検討した.MRSAの分離は半数以上を占めているものの1997年以降分離株数に変化はなかった.一方Enterococcus,Klebsiellaの分離株数は有意に増加していた.1999年から2000年に分離された症例において,感染症の起炎菌となっているかどうかを検討した結果,Enterococcus faecalisでは38症例中12症例(31.8%),Enterococcus faeciumは10症例中0症例,Klebsiella oxytocaでは20症例中6症例(30.0%)が起炎菌と考えられた.Enterococcus,Klebsiellaは近年耐性菌として注目されている.当院NICUにおいて,これらが起炎菌となっている症例も少なくなく,MRSA以外の耐性菌にも今後目を向けていく必要があると思われた.これらの菌の耐性化を進ませないために,抗菌剤の使用には注意を要する. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 就学前幼児に対する不活化インフルエンザワクチンの2流行期における成績 |
| ■著者 |
宍粟総合病院小児科
前田 太郎 |
| ■キーワード |
| インフルエンザ,インフルエンザワクチン,幼児 |
| ■要旨 |
| 小学校就学前の幼児における不活化インフルエンザワクチンのA型インフルエンザに対する予防効果を2回の流行期にわたって調査した.流行期前までにワクチンの接種を終えた幼児(2歳以上7歳未満)とワクチン接種を受けていない幼児と追跡比較した.1999/2000年の発病率はワクチン群で3.8%,対照群で18.6%であり(p=0.013),2000/2001年ではワクチン群が1.8%,対照群が8.3%(p=0.036)で,いずれの年でもワクチン群で有意に低かった.2シーズンの合計で有効率80.5%,p=0.00054と就学前の幼児においても成人に接種した場合と同様に発病阻止効果が認められた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 乳幼児突発性危急事態児の心拍変動解析 |
| ■著者 |
東京女子医科大附属第二病院小児科1),同院 内科2)
| 数間 紀夫1) |
大塚 邦明2) |
野崎 真紀1) |
若松 敬子1) |
| 中村江里奈1) |
松岡 郁美1) |
杉原 茂孝1) |
|
|
| ■キーワード |
| 心拍変動,乳幼児突発性危急事態,MemCalcシステム,自律神経機能,1/fゆらぎ |
| ■要旨 |
| 乳幼児突発性危急事態(ALTE)児の心拍変動解析を行った.1994年から1999年の6年間に入院した1〜6カ月のALTE 23例と対照25例を対象に,24時間ホルター心電図記録をし,MemCalc/Chiram(GMS社)によって,24時間の時間領域および周波数領域における心拍変動を比較した.さらに周波数とそのパワースペクトル密度から得られる1/f βゆらぎの中,特にβが1前後である1/fゆらぎについて検討した.ALTE群と対照群では時間領域および周波数領域のいずれの指標にも有意差がみられなかったが,β値はALTE群の傾きが大きかった(ALTE群1.29±0.1,対照群1.88±0.13:t=3.13,p=0.003).さらに1/fゆらぎがみられなかった(βが成人の正常値の範囲になかった)例はALTE群で11例(47.8%),対照群で6例(24%)であった.1/fゆらぎは非線形解析のひとつであり,ALTEにおける生体制御系を表現する新たな指標となる可能性がある. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 胃十二指腸潰瘍33例の後方視的観察 |
| ■著者 |
東邦大学医学部第一小児科学教室,防衛医科大学校小児科*
橋本 卓史 蜂矢 正彦 月本 一郎 藤澤 知雄* |
| ■キーワード |
| 消化性潰瘍,Helicobacter pylori,除菌療法 |
| ■要旨 |
| 21年間に当院で経験した小児の胃十二指腸潰瘍33例の臨床経過について後方視的に検討した.患者は発症時5カ月から15歳,現在3歳から29歳の男性23例,女性10例で,胃潰瘍17例,十二指腸潰瘍16例(一次性潰瘍26例,二次性潰瘍7例)であった.十二指腸潰瘍は胃潰瘍に比べて合併症を有することが多かった.1例が穿孔のため,他の1例が基礎疾患のため死亡し,生存している31例中27例の長期的転帰が確認できた.7例が再発し,その特徴は発症時年齢が10歳以上,一次性十二指腸潰瘍,Helicobacter pylori陽性であった.二次性胃潰瘍は再発率が低く,Helicobacter pylori陰性であった.Helicobacter pylori陽性の一次性十二指腸潰瘍例は初発例でも除菌療法の適応と考えられる. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 感染時脳梗塞を発症し抗リン脂質抗体陽性を呈した1歳男児例 |
| ■著者 |
県立広島病院小児科
| 木原 裕貴 |
坂野 堯 |
松原 啓太 |
| 木下 義久 |
大田 敏之 |
濱崎 隆 |
|
| ■キーワード |
| 脳梗塞,抗リン脂質抗体症候群,抗カルジオリピン抗体,感染症 |
| ■要旨 |
| 症例は1歳男児.感冒様症状とともに右片麻痺がみられ,頭部MRIなどから左被殻の多発性脳梗塞と診断した.原因検索の結果,血中抗β2グリコプロテインI依存性抗カルジオリピン抗体(aCL抗体)は陰性であったが,aCL-IgGが陽性であった.初発症状は数日で改善したが,44日後,感冒様症状に引き続き軽度の右片麻痺が一過性にみられた.本症例は,感染を契機として症状発現する抗リン脂質抗体症候群が強く疑われた.初発時に咽頭よりコクサッキーB3が分離されたが,aCL抗体産生との直接の因果関係は不明である.本症例は,アスピリン少量投与で再発をみていないが,今後も十分な経過観察が必要である. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 免疫グロブリン大量静注療法が寛解維持に有効であった多発性硬化症の1例 |
| ■著者 |
埼玉医科大学総合医療センター小児科
| 泉田美知子 |
佐野 仁美 |
岡野 俊季 |
新田 啓三 |
| 高山千雅子 |
菅原志保子 |
渡辺 王志 |
板倉 敬乃 |
| 清水 浩 |
小川雄之亮 |
|
|
|
| ■キーワード |
| 多発性硬化症,免疫グロブリン大量静注療法,Expanded Disability Status Scale |
| ■要旨 |
| 免疫グロブリン大量静注療法(intravenous immunoglobulin:IVIg)が寛解維持に有効であった多発性硬化症(multiple sclerosis:MS)の1例を経験した.患児は精神遅滞のあった13歳女児,両下肢痛で発症し不全対麻痺,膀胱直腸障害,視力低下を示し脳MRIでT2高信号域の多発を認めた.Methylprednisolone(mPSL)パルス療法で独歩可能となったが,以後も感染を契機に急性増悪を繰り返し,発症から17カ月の間に計5回再燃し計11回のパルス療法を必要とした.再燃予防の目的で1999年12月より4週に1度のIVIg(0.2g/kg)を開始し,投与間隔を徐々に延ばして2001年8月までに計13回のIVIgを施行したところ,2001年10月現在まで約22カ月間再燃なく寛解状態を維持している.Expanded disability status scale(EDSS)は,IVIg開始後7.5から4.0と改善した.MSの再燃防止治療として,IVIgは極めて有効な治療法と考えられた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| Refeeding syndromeによりけいれん重積をきたした神経性食欲不振症の1例 |
| ■著者 |
防衛医科大学校小児科
| 大川 貴司 |
藤塚 聡 |
赤木 稔 |
| 古池 雄治 |
関根 勇夫 |
|
|
| ■キーワード |
| 神経性食欲不振症,けいれん,refeeding syndrome,低リン血症,道具的条件付け療法 |
| ■要旨 |
| 症例は14歳の女児.著明な体重減少,病識の欠如,無月経などから神経性食欲不振症(AN)と診断した.道具的条件付け療法と経管栄養を開始したところ,翌日から抑うつやせん妄状態などの精神症状,さらに治療開始3日後から5日後にかけてけいれんが3回出現した.3回目のけいれん時の脳波検査で全般性の棘徐波を認め,また重度の低リン血症を合併していた.リン製剤の補充が症状の改善に著効した.退院後は脳波検査などに異常なく,精神神経症状が一過性であったことから,refeeding syndrome(RS)によるけいれんであったと診断した.小児のANでは行動療法的アプローチが効果的で,本例のように積極的に食事を摂ることがRS合併の一因となりうる.また,治療開始時から充分なリン製剤を補充し,経管栄養を併用する場合には栄養が急速に負荷されないよう管理することが重要である. |

|
| 【短報】 |
| ■題名 |
| インフルエンザ罹患児における中耳炎の病態 |
| ■著者 |
東北労災病院小児科1),同 耳鼻科2)
| 遠藤 廣子1) |
高柳 玲子1) |
中澤 千冬1) |
| 小島三千代1) |
末武 光子2) |
|
|
| ■キーワード |
| インフルエンザ,急性中耳炎,抗インフルエンザ薬,迅速診断,二次性細菌感染 |
| ■要旨 |
アマンタジン投与を行ったインフルエンザA罹患小児63例のうち,急性中耳炎の合併は6例(9.5%)だった.一方,抗インフルエンザ薬使用のないインフルエンザB罹患81例の急性中耳炎合併は24例(29.6%)であり,抗インフルエンザ薬が中耳炎の発症を防止していた.
インフルエンザB発症1〜6病日に中耳炎と診断された17例で中耳貯留液にてFlu OIA検査を行い16例が陽性であった.細菌培養では2病日以降に病原細菌が分離され,早期に二次性細菌感染が起こることが判明した. |
|
バックナンバーに戻る

|

