 |
日本小児科学会雑誌 最新号目次  |
第105巻 第9号/平成13年9月1日
Vol.105, No.9, September 2001
バックナンバーはこちら
|
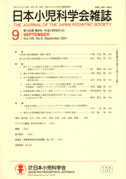 |
|
|

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 低カルシウム血症を主所見とした乳児早期のビタミンD欠乏症―母親のビタミンD欠乏の関与― |
| ■著者 |
大阪大学大学院医学系研究科生体統合医学小児発達医学小児科1),
大阪厚生年金病院小児科2),兵庫県立西宮病院小児科3)
| 島 雅昭1) |
平井 治彦1) |
志水 信彦1) |
中島 滋郎1) |
| 西村 久美1) |
小林めぐみ2) |
田川 哲三2) |
田中 能久3) |
| 安部 治郎3) |
岡田伸太郎1) |
|
|
|
| ■キーワード |
| ビタミンD欠乏,25OHD,副甲状腺ホルモン,テタニー |
| ■要旨 |
| 乳児早期に低カルシウム血症を主所見としたビタミンD欠乏症の3例を経験した.これらの3例は,early hypocalcemic typeのビタミンD欠乏症と考えられ,日齢34から81にテタニーで発症した.3例とも混合栄養で保育されていた.血清カルシウム値は著明に低下していたが,低リン血症は1例のみで認められた.いずれも手根骨レントゲンでくる病を呈していなかった.ビタミンD欠乏の原因として児の外出制限とビタミンDの吸収障害に加えて,母親のビタミンD欠乏の関与が考えられた. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 過去6年間の麻疹の流行について |
| ■著者 |
札幌医科大学医学部小児科
|
| ■キーワード |
| 麻疹,乳児麻疹,年長児麻疹,primary vaccine failure,secondary vaccine failure |
| ■要旨 |
| 近年の北海道における麻疹の流行状況を明らかにするために,1995〜2000年にかけて,毎年,アンケート調査を行い合計1,015例の麻疹患者の報告を受けた.うち1歳未満の乳児麻疹が187例(18.4%),10歳以上の年長児の麻疹が145例(14.3%)を占めたが,この割合は麻疹ワクチンの定期接種が開始して数年が経過した1980年代前半の乳児麻疹および10歳以上の年長児麻疹の割合に比較し明らかに増加していた.ワクチン接種者は約5%でありほとんどがワクチン未接種者であった.未だ予防接種率が十分に高くないことが流行が繰り返される原因と考えられた.乳児麻疹の対策のため予防接種開始年齢の引き下げが考えられるが,現時点では1歳以降の児の接種率を向上させ流行を阻止することが急務と考えられた.具体的な方策の一つとして1歳半健診,3 歳児健診や就学児健診の時点でワクチン接種の有無をチェックし,接種を勧めることがあげられる. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 先天性僧帽弁狭窄の人工弁置換術後に高度の右心不全を来した一卵性双生児 |
| ■著者 |
徳島大学医学部小児科
|
| ■キーワード |
| 先天性僧帽弁狭窄症,パルスドプラ法,肺静脈血流 |
| ■要旨 |
先天性僧帽弁狭窄の一卵性双生児の乳児例に対して,僧帽弁輪より上方(supra annular)に人工弁置換を施行した.術後,人工弁機能は正常にもかかわらず左房圧波形のV波は高値で,肝腫大・腹水などの高度の右心不全が持続した.1例に施行した心臓カテーテル検査では左房容積が小さく,一心周期の容積変化も少なく左房のコンプライアンスの低下が疑われた.心エコーパルスドプラ法による肺静脈血流では心室拡張期波が主体で,心室収縮期波は低速または逆方向を示し,左房のリザーバー機能の低下が考えられた.
乳児期の僧帽弁狭窄に対する僧帽弁輪より上方の弁置換術では,術後に右心不全が持続する例があり,その評価に心エコーパルスドプラ法が有用である. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 二次性のI型高脂血症,インスリン自己免疫症候群,自己免疫性甲状腺炎,全身性エリテマトーデスを合併した女児例 |
| ■著者 |
山口県厚生連小郡第一総合病院小児科1),山口県立中央病院小児科2),
山口大学医学部保健学科3)
| 杉尾 嘉嗣1) |
井出 文仁1) |
前場 進治1) |
杉尾 陽子2) |
| 塚原 正人3) |
|
|
|
|
| ■キーワード |
| I型高脂血症,自己免疫性高カイロミクロン血症,インスリン自己免疫症候群,全身性エリテマトーデス,自己免疫性甲状腺炎 |
| ■要旨 |
| 自己免疫機序により発症したと考えられるI型高脂血症,自己免疫性甲状腺炎,インスリン自己免疫症候群,全身性エリテマトーデスを合併した9歳女児を報告した.本児は4歳で甲状腺機能亢進症を発症し,I型高脂血症(トリグリセライド954mg/dl)を合併していた.リポ蛋白リパーゼ(LPL)は20ng/dl以下であった.7歳から甲状腺機能が低下し始め,8歳時に血小板減少症を合併し,同時に低補体価,抗核抗体陽性,抗DNA抗体陽性を認めた.メチルプレドニゾロンのパルス療法施行後,高脂血症は消失し,LPLは正常化した.高脂血症はLPLに対する自己抗体により発症する自己免疫性高カイロミクロン血症と考えた.また,空腹時の低血糖とインスリン抗体を認め,インスリン自己免疫症候群と診断した.自己免疫疾患では,自己抗体により予期せぬ症状が出現する可能性がある. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 抗精神病薬の誤飲により一過性パーキンソニズムを呈した1幼児例 |
| ■著者 |
東邦大学付属佐倉病院小児科
|
| ■キーワード |
| パーキンソニズム,薬物誤飲,ハロペリドール |
| ■要旨 |
| 症例は2歳8カ月の女児.約半日のうちに進行した体幹の硬直と無表情を主訴に来院した.来院時に錐体外路症状を認めたが,入院30時間後に症状は改善した.詳細な病歴聴取および診察所見より薬剤誘発性パーキソニズムが疑われ,血中濃度測定により確定診断に至った. |

|
| 【原著】 |
| ■題名 |
| 診断及び経過観察に頭部MRI検査が有用であったshaken baby syndromeの1例 |
| ■著者 |
防衛医科大学校小児科
| 堀内 勝行 |
竹下誠一郎 |
安國 真理 |
| 川村 陽一 |
関根 勇夫 |
|
|
| ■キーワード |
| Shaken baby syndrome,MRI,乳児,頭蓋内出血,眼底出血 |
| ■要旨 |
| 生後2カ月のShaken baby syndromeの1男児例を経験した.父親が患児を「たかい,たかい」をしてあやした後に,突然の痙攣で発症した.入院時の頭部CT検査では明らかな所見を認めなかったが,頭部MRI検査で小脳テント下の小出血を認め,眼科的に左眼の網膜前出血と網膜出血がみられた.発症2週間後の頭部MRIで左前頭から側頭部にかけての硬膜下出血を認めたが,発症5カ月後には血腫は消失した.脳圧降下剤及び抗痙攣剤投与による保存的治療のみで軽快し,その後成長発達に異常は認めていない.本症例は被虐待の既往がなく,日常の養育的行為によって偶発的に発症したShaken baby syndromeと考えられた.また,本症の診断とその経過観察に,頭部MRI検査が有用であった. |

|
| 【短報】 |
| ■題名 |
| 7.0歳児を対象にしたインフルエンザワクチン接種における抗体獲得について |
| ■著者 |
星川小児クリニック1),吉村小児科2),小児科高橋医院3)
|
| ■キーワード |
| インフルエンザワクチン,HI抗体価,乳児 |
| ■要旨 |
| 2000年に出生した生後5カ月から10カ月の乳児を対象に,2000年10月からインフルエンザワクチンの接種を行い,ワクチン株に対するHI抗体を測定した.その結果40倍以上の抗体価を得た児は,A(H1N1),A(H3N2),B型インフルエンザウイルスに対して,56%,24%,48%であり,特にA(H3N2)型に対する抗体獲得が極めて悪かった.今後,乳幼児の接種を効果的にすすめるためにも,接種量も含めた接種方法の再検討が望まれる. |

|
| 【短報】 |
| ■題名 |
| 8.最近の小児科臨床現場で直面したネグレクト症例の検討 |
| ■著者 |
昭和大学医学部小児科1),千葉県こども病院新生児科2)
| 古荘 純一1) |
子安ゆうこ1) |
森田 孝次1)2) |
神谷 雄己1) |
| 水谷 佳世1)2) |
今井 孝成1) |
高村まゆみ1) |
飯倉 洋治1) |
|
| ■キーワード |
| ネグレクト,医療ネグレクト,虐待防止法案 |
| ■要旨 |
| 適切な医療を受けなければ子どもが死に至る可能性があるにも関わらず,保護者が医療を拒否したネグレクトの3例を経験した.これらの事例に対応するには,主治医の努力のみでは困難であり,児童福祉法や虐待防止法の周知とそれに基づいた通告,専門機関との連携やネットワークへの積極的な参加,症例ごとの検討,などの対応が必要と考えられる.著者らはこれを,保護者の「医療ネグレクト」と提唱して医療関係者等に喚起を促したい. |
|
バックナンバーに戻る

|

